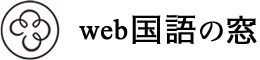教科書編集委員の先生から「現代の国語」
明治書院の新しい「現代の国語」は、どのような思いで作られたのか。 ポイントを各分野の先生に語っていただきました。
論理的な文章
十重田裕一(早稲田大学教授)
明治書院の「現代の国語」は、高等学校で学んで欲しい基礎学力が身につくように工夫して編集してある。生徒たちが「現代」の社会を生きていくうえで役立つと同時に、多様な進路に対応できるようなテーマを各章のタイトルにした。「1章 ことば・思考」「2章 自己・他者」「3章 芸術・文化」「4章 情報・メディア」「5章 哲学・思想」「6章 環境・自然・生命」「7章 経済・社会」「8章 世界・平和」「9章 言語・歴史」の各章に厳選、収録した文章はいずれも、「現代」の教養が身につく、生徒たちの未来に役立つ魅力的な日本語で書かれている。長田弘「自分の時間で読み継ぐ」を冒頭に配したのは、繰り返し読むことの重要性を生徒たちに伝えたいからである。長田氏はこの文章の中で、「自分の日々の時間の傍ら」に置いて「繰り返し読みさす」ことの大切さを述べている。生徒たちが「現代の国語」を傍に置いて、収録された文章を繰り返し読みさせば、「現代」を生きていくための知恵と思考が着実に伸びてゆくに違いない。
単元の言語活動
坂口陽子(富士見丘中学高等学校)
目まぐるしく変動していく時代を生き抜くために、今「国語のグローバル化」が求められています。グローバルな国語力とは、誰しも納得できる説得力や論理性の高い意見を相手に分かりやすく伝える力のことです。
「単元の言語活動」では、読むだけでなく、考え、発信し、相互評価して、さらにそれを改善するという活動を行います。正しく読解し、深く考える力は、書いたり話したり、表現することによって着実に身に着けることができます。
また、実社会では、論説文や説明文だけでなく、さまざまな種類の文章に向き合い、必要な情報を読み取る力が必要になりますが、明治書院の「現代の国語」には、単元ごとに教材に合わせた実用的な文章が載っています。自分の考えを文章化することはもちろんですが、写真や図表を用いた説明資料を作成する体験などを通して、実社会に生かせる情報発信の技術を身につけ実践的な国語力を磨きましょう。
書くことの窓
石黒 圭(国立国語研究所教授)
二〇二二年度から実施される学習指導要領の改訂により、高等学校の国語教科書は、言語技術をみがく方向に大きく舵を切りました。中でも、重視されているのが「書く力」です。
現代の高校生は「打つ力」には長けています。スマホを使って友人と文字を送り合う日々の中で、気持ちを伝え合うために日常的な文章を短く打つのは得意です。しかし、読み手を説得するために論理的な文章を長く書くのは苦手で、特に次の四つの力が不足しています。
①文脈に合った言葉を吟味し、適切に選択する力
②一貫性を持って、文章全体を構成する力
③読み手の知識を想定して、分かりやすく書く力
④洗練された文体で、書き言葉にふさわしく書く力
明治書院の「現代の国語」では「書くことの窓」というコラムを通して①〜④の文章力向上の支援を行います。
高校時代の学びに留まらず、大学進学後の論文・レポート、さらには就職後のビジネス文書の執筆力につながる真の「書く力」を、この時期にしっかり鍛えておく。本書にはそのためのエッセンスがぎっしり詰まっています。
|
「書くことの窓4」(『新 精選 現代の国語』P.208-209) |