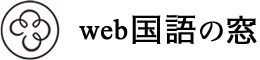高校国語 新しい時代に対応した国語科教育の方向性 国語科の存在意義を再考する
大滝 一登 編著(A5判、280頁、定価3,850円(3,500+税10%) 好評発売中!
これまでの数十年にわたる改訂の経緯・これからの国語科の課題と改善策!
|
目次
【第1章】学習指導要領のこれまでとこれから
①はじめに
②筆者自身の国語教育観の形成と深化を振り返って
③改めて高校国語の課題を確認する
④現行学習指導要領の改訂から告示までを振り返る
⑤学習指導要領の実施によって変わったこと変わらなかったこと
⑥高校国語における「話すこと・聞くこと」「書くこと」の現在地点
⑦「論理か文学か」論争について
⑧根強い「古典不要論」に高校国語はどう立ち向かえるのか
⑨国語科の必要性が十分認識されるためには
⑩おわりに
•大滝一登(安田女子大学教授)
【第2章】新しい時代の国語科教育を探る論点
論点1 育成を目指す資質・能力に対する教師の認識と観点別学習状況の評価の現在
①観点別学習状況の評価とは
②資質・能力の育成を図る観点別学習状況の評価の実際
•髙木展郎(横浜国立大学名誉教授)
論点2 高校国語と教科書との望ましい関係とは
①奇妙な存在、国語科教科書⑴―「言論の場」から考える
②奇妙な存在、国語科教科書⑵―「学習の場」から考える
③国語科教科書における読解
④オンライン空間の登場による変化
⑤ではどうすればいいか―ロードマップ再考
•難波博孝(安田女子大学教授・広島大学名誉教授)
論点3 国語科教育研究は新しい時代に対応できるか
①シシガミの森
②消えゆくものと生まれるもの
③消えゆくものと生まれるものとのはざまで
④国語科教育研究の現状と課題
⑤2つの道の止揚
⑥シシガミは花咲爺だった
⑦不易流行
•藤森裕治(文教大学教授)
【第3章】新しい時代の課題に立ち向かう論点
論点4 国語科と「探究」、他教科等との求められる関係性
①「探究」と国語科教育
②地歴科教員との対談から
③学習塾を運営する教師との対談から
④高等学校国語科の明日をひらくために
•幸田国広(早稲田大学教授)
論点5 これからの大学入試と求められる「国語」の力
①大学進学をめぐる状況
②大学入学共通テスト
③3つの試験区分による入試
④大学入試で求められる「国語」の力
•島田康行(筑波大学教授)
論点6 「教員不足」時代の国語科教師教育の在り方
①はじめに
②国語科における教員不足
③国語科教師の専門性
④研修観の転換
⑤国語教師の現在
⑥教育委員会における研修の状況
⑦教員研修における実践
⑧生徒にとっての重要なロールモデルとなるために
•倉田 寛(学校法人堀井学園横浜翠陵中学高等学校副校長)
論点7 コロナ禍が進めたICTの現在地
①はじめに
②教員研修におけるICTの活用
③授業におけるICTの活用
④今後の展望と国語科の存在意義
•鎌田康平(北海道教育長学校教育局高校教育課高校教育指導係長)
論点8 カリキュラム・マネジメントのために今日からできること
―学校経営からみた高校国語の現状と課題①―
①学校教育計画と国語科
②求められる国語の力とは
③国語の力をどのように身に付けていくか
④授業研究の事例より
⑤国語科のカリキュラム・マネジメント
⑥学びを支える言葉の力
⑦カリキュラム・マネジメントのために今日からできること
⑧国語科としての探究的な学び
•松澤直子(神奈川県立総合教育センター教育事業部長)
論点9 育てたい生徒像を共有した学校づくりが授業改善を導く
―学校経営からみた高校国語の現状と課題②―
①カリキュラム・マネジメントと高校国語科の関係
②専門学校における言語能力の育成に係るカリキュラム・マネジメント
③校内外の多様な人々による「聞くこと」の実践的な場面の拡大
④国語科の授業で育成する「対話する力」
⑤生徒のアウトプットを中心とした教育活動への展開
⑥普通科高校における言語能力の育成に係るカリキュラム・マネジメント
⑦カリキュラム全体を見据えて国語科の年間指導計画を構築する
⑧カリキュラム全体を見据えて国語科と探究の関係を模索する
⑨育てたい生徒像を共有した学校づくりが授業改善を導く
•渡邉本樹(福井県教育庁高校教育課課長)
論点10「個別最適な学び」と「協働的な学び」、実社会を意識した学習指導
―次期学習指導要領を見据えたこれからの授業改善①―
①生徒が「実社会」を生き抜くために必要な言葉の力
②生徒が「主体的に学習に取り組む」授業で「実社会」とつなげる
③必履修科目の領域の時間数と「実社会」で必要となる能力の相関
④いわゆる「進学校」の授業改善(実践ベース・「論理国語」の授業による考察)
⑤次期学習指導要領を見据えた授業改善(提案ベース・「現代の国語」の授業の例示)
⑥生徒が生き生きと学ぶ姿を想像した授業づくり
•佐藤治郎(神奈川県立川和高等学校教諭)
観点11「個別最適な学び」と「協働的な学び」、言語の文化性を意識した学習指導
―次期学習指導要領を見据えたこれからの授業改善②―
①はじめに(現行の学習指導要領改訂で求められたこと)
②言語の文化性を意識した授業における「個別最適な学び」と「協働的な学び」とは
③「授業改善」のこれから
④次期学習指導要領に向けた授業改善
•石原徳子(栄光学園中学高等学校非常勤講師)
【第4章】次期学習指導要領の方向性
①はじめに
②今後の教育課程、学習指導及び学習評価等の在り方に関する有識者検討会の論点整理について
③中央教育審議会への諮問「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について」
④学習指導要領実施状況調査の結果等を踏まえた国語科の成果と課題―義務教育を中心に―
⑤おわりに
•上月さやこ(文部科学省初等中等教育局教育課程課教科調査官・国立教育政策研究所教育課程研究センター研究開発部教育課程調査官・学力調査官)
執筆者・執筆箇所一覧