セイゴンの夜③「熾熱灯の光が豊太郎にはなぜ《徒》に見えるのか」
熾熱灯の光が豊太郎にはなぜ「徒」に見えるのか
主人公・太田豊太郎の搭乗したフランス国籍の豪華客船の二等cabinの共用空間に置かれている卓の周囲が静寂である理由は、次の第三文に説明されている。「今宵は夜毎にこゝに集ひ来る骨牌仲間も「ホテル」に宿りて、舟に残れるは余一人のみ」だからだよね。「一人のみ」の下の「なれば」は断定の助動詞「なり」の已然形「なれ」と、原因・理由を著す接続助詞「ば」。「…であるから」という意味でしょ。少しカッコつけていうと、ここは、第二文と第三文が倒置法によって構成されている構文になっているというワケ。「熾熱灯の光の晴れがましきも徒なり」というのは、いつもは熾熱灯の下で楽しく骨牌に興ずる人たちがいないから…

「つまり、いつもの賑やかさがうそのようにcabin内が静まりかえっているので、煌々と照る熾熱灯の光が空しく感じられる、というんでしょ。」
 おそらくこういう経験はだれも持ってるんじゃない?
おそらくこういう経験はだれも持ってるんじゃない?
たとえばさ、さっきまで煌々と照る照明灯の下で、観客の歓声に包まれて行われていた野球とかサッカーとかのゲームも終わり、選手もグランドから姿を消し、スタンドの観客もほとんどまばらになったスタジアムの夜光灯の光が寂しげに感じられる、というような。
当時の外国航路就航の二等cabinが六人部屋の船があったということは前回書いた。仮に豊太郎の乗った船もそういう構造だったとしたら、豊太郎のcabinはきっと、お互い特別の関係もない人たちの「相部屋」ではなく、天方大臣に随行して帰国する人たちが寝泊まりしていた「貸し切りcabin」だったのではないか。そのcabinに、「骨牌仲間」が「夜毎に集ひ来」ていたというのだから、たぶんその「骨牌仲間」には外のcabinに寝泊まりしている同行の随行者もいたんじゃないか。

「そういう毎晩毎晩賑やかなcabinのなかで、豊太郎はいつもどうしていたの?」
そもそも豊太郎は、天方大臣の最初からの随行員ではない。たまたまその高い語学力を大臣に買われて、大臣一行と一緒に帰国の途にある一人の人間にすぎない。豊太郎が明朗で快活で、だれとでもすぐ親しくなれるようなそういうタイプの人間ならば、外の随行員ともすぐ打ち解けただろう。しかし彼はそういう性格の人間ではなかった。
「わが心はかの合歓といふ木の葉に似て、物触れば縮みて避けんとす。わが心は処女に似たり」というような、極めてデリケートな神経の持ち主だった。だから豊太郎は、「世の常ならば生面の客にさへ交を結びて、旅の憂さを慰めあふが航海の習なるに、微恙にことよせて房の裡にのみ籠りて、同行の人々にも物言ふことの少なき」帰国の旅の日々を送っていたのだ。
だから彼は、「夜毎にこゝに集ひ来る骨牌仲間」と一緒に彼も骨牌に興じ骨牌を楽しんでいたとは思えない。そういう人間にとって、cabinに一人取り残されること自体は彼のストレスを惹起する要因にはたぶんならない。いや、むしろ彼はほんとうは、逆にサイゴン港の夜のcabin内での孤独を歓迎していたとも考えられる。
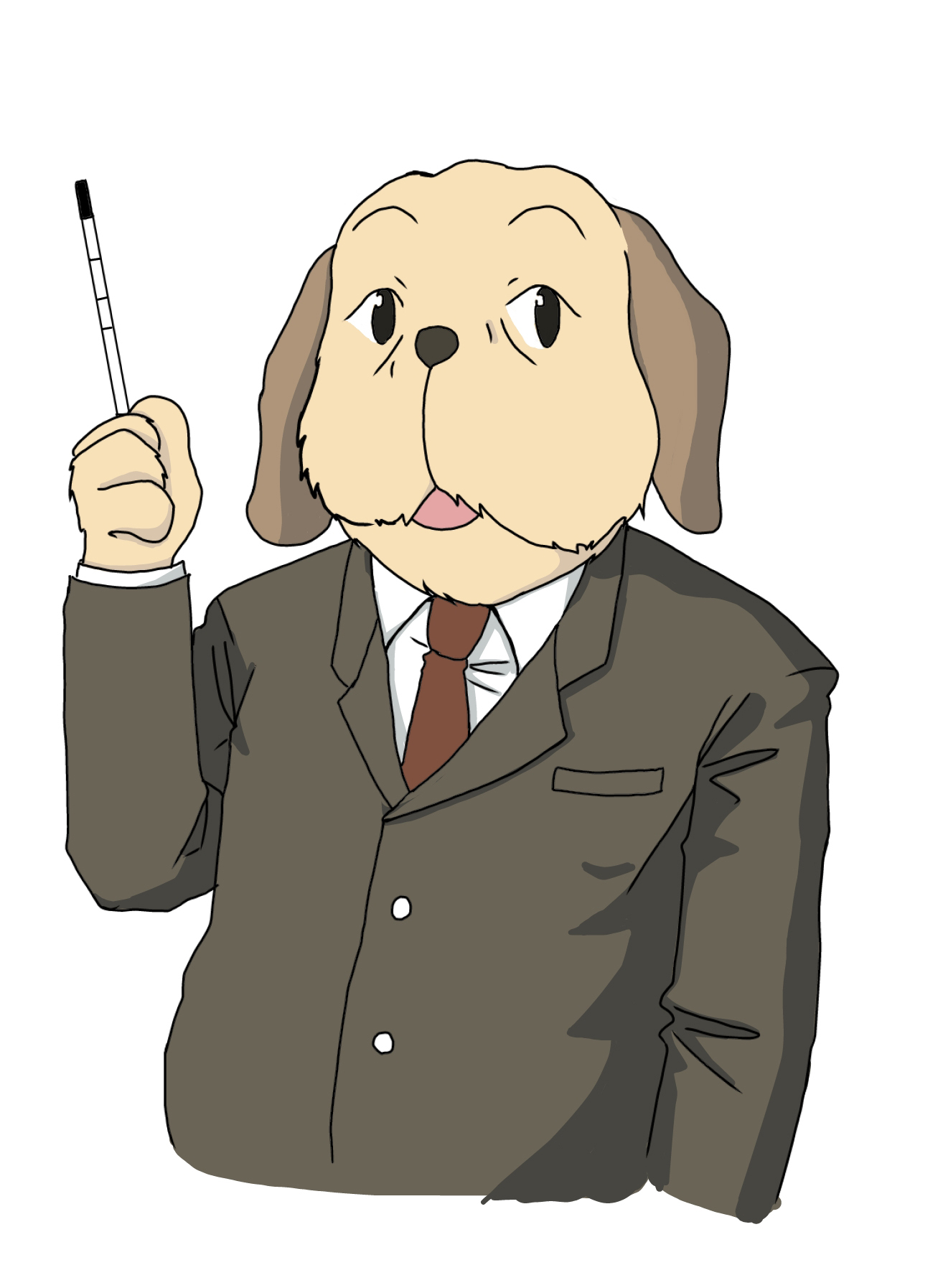 なら、何が豊太郎に「熾熱灯の光の晴れがましきも徒なり」と思わせたのか。それは、このとき豊太郎が「人知らぬ怨に頭のみ悩まし」ていたからだという理由以外に考えようもない。そういう豊太郎を一人cabinに残し、外の随行員たちは、明日はいよいよ日本に向けて出航というその夜、「ホテル」に宿泊するため、船から陸に上がったという。なんのためか。まなちゃんはなんのためだと思う? おじいちゃんはね、この夜陸に上がって「ホテル」に宿泊したのは随行員だけじゃないんじゃないかと思ってるんだよ。つまりね、天方大臣もこの夜、ある目的をもって「ホテル」に泊まっているんじゃないかという気がする。もちろんおじいちゃんのそういう推測に、確実な根拠があるわけじゃない。ただ、そういう気がする、というだけの話なんだが、でも、そう考えると、他のいろんなことがスムーズに納得できるんだよ。そのことはまたいずれ話さなければならないだろうが、いまはこの程度にとどめておきたい。
なら、何が豊太郎に「熾熱灯の光の晴れがましきも徒なり」と思わせたのか。それは、このとき豊太郎が「人知らぬ怨に頭のみ悩まし」ていたからだという理由以外に考えようもない。そういう豊太郎を一人cabinに残し、外の随行員たちは、明日はいよいよ日本に向けて出航というその夜、「ホテル」に宿泊するため、船から陸に上がったという。なんのためか。まなちゃんはなんのためだと思う? おじいちゃんはね、この夜陸に上がって「ホテル」に宿泊したのは随行員だけじゃないんじゃないかと思ってるんだよ。つまりね、天方大臣もこの夜、ある目的をもって「ホテル」に泊まっているんじゃないかという気がする。もちろんおじいちゃんのそういう推測に、確実な根拠があるわけじゃない。ただ、そういう気がする、というだけの話なんだが、でも、そう考えると、他のいろんなことがスムーズに納得できるんだよ。そのことはまたいずれ話さなければならないだろうが、いまはこの程度にとどめておきたい。
… で、「ホテル」。
「ホテル」について
この「ホテル」という語に「 」がついてる教科書と、ついてない教科書とあると思うが、まなちゃんの教科書はついてるかな。ほんとはきちんと「 」をつけてほしいんだけどね。
—— なぜかというとこんなワケさ。
|
鷗外は『舞姫』という作品を何回か書き換えてるのだが、一貫して守ってきた表記法があった。それは、外国人名には、エリスというように一重傍線、外国地名にはベルリンというように二重傍線を付けた。それから「ニル・アドミラリ」「マンサルド」「ゾファ」「カバン」などの、その語を日本語表記するのが不適当と思われる語には「 」を付けた。「ホテル」もその一つ。 幕末から明治にかけて、実に夥しい外国語が日本語に翻訳されたことは、まなちゃんも知っておろう。そういう語の中には鷗外が訳した語もあるそうだ。たとえば「情報」、「交響曲」など。「ホテル」は日本語に訳せばさしずめ「旅籠(はたご)」「宿屋」「旅館」ぐらいだろうか。しかしそれらの語で表される施設と〔ホテル〕とではやはり決定的相違があったのではあるまいか。まなちゃんもいつだったか行ったことがあったよね、東海道の岡部と新居の宿の「旅籠」を見にさ。「旅籠」はやっぱり「水戸黄門」の世界じゃない? 「旅館」だってその言葉によってメイージされるところは「ホテル」とは全然違うようにおじいちゃんは思うが…。 だからそういう語に鷗外は「 」をつけたんだよ。その「 」には日本の文化と西洋の文化との違いに注意して読んで欲しい、「 」を付けた語を無理に日本語にすると、そのものの実態が歪められるから、敢えて外国語のままにしておくよ、という鷗外の気持ちが込められているんだよ。〔カバン〕なんて言葉も、当時の他の作家の作品には「革手提(かわてさげ)」なんて漢字を充てているものもあるけど、それじゃあ「カバン」のイメージがわいて来なかろう。後ろの方に出てくる「カイゼルホオフ」という、天方大臣が泊まっていたホテルは当時のベルリンのホテルでも、超一流のホテルだった。内部構造は作品の中で少しだけ紹介されてるよね。 |

「天方大臣の随行者たちが、出航前夜に宿泊したセイゴンのホテルはどんなホテルだったの?」
そういう「ホテル」も、今では日本全国どこにもある。けれども豊太郎が洋行していた明治20年前後の時代には、「ホテル」なんて、どこにもあったわけじゃない。日本で最初にできた「ホテル」は、明治元年に竣工した「築地ホテル館」だった。ところがそのホテルも、鷗外が津和野から上京してきた明治5年に火災でなくなっちゃった。正面の横幅約76㍍、奥行約72㍍、高さ約28㍍だったというから、当時としてはかなり立派な建物だったと思う。その年、築地に「西洋館ホテル」(精養軒ホテル―築地精養軒)が開業した。
その後は、『舞姫』が執筆された明治22年に「ホテル愛宕館」、『舞姫』発表の明治23年「帝国ホテル」「東京ホテル」が落成した。だけどね、そんな「ホテル」になんてね、誰でも泊まれたワケじゃない。
おかしな話だけどね、半世紀ほど前、昭和39年の東京オリンピック開催に合わせて東海道新幹線が開業した。当時おじいちゃんは東京で学生生活を送っていたんだが、新幹線に乗れる人ってさ、お金持ちの人しか乗れないんだって、ほんとにそう思ってた。おじいちゃんの友だちで、帰省するとき新幹線で帰った人もお金持ちだったしさ。おかしい?だけどおじいちゃんと同じように思っていた人って、その当時たくさんいたと思うよ、ほんとに。
明治の「ホテル」って、一般の庶民の泊まれる施設じゃない、ごく一部の人しか泊まることのできない、そういう施設だってことは承知しておくべし。だから、「カイゼルホオフ」に泊まった人も、セイゴンの「ホテル」に泊まった人も、ある意味、特権階級の人でさ。
けど、考えてみれば豊太郎だって本来はそういう人でしょ。彼は「旧藩の学館」つまり「藩校」で勉強できた人だし、東大法学部を首席で卒業して内務省か司法省かどちらかの、中央官庁で働く「超エリート」でござろう。そういう人がね、それにふさわしいプライドを持ってないなんて、ちょっと考えられない。むしろ、「ホテル」に泊まれるような人って、「プライドの塊」みたいな人だと思ってまずまちがいないと思う。そのことは、『舞姫』にも描かれているよね。
 ところでね、鷗外の短編小説に『普請中』って作品がある。明治42年に発表された。主人公は「渡辺参事官」。『舞姫』の太田豊太郎の「その後」を書いたような作品でね、ドイツにいたころ交際した女性が渡辺を訪ねてきて、「精養軒ホテル」で夕食をともにする、という話。その中に「ホテル愛宕館」と思われるホテルも登場する。短編だし、『舞姫』のような文体ではなく、いまの普通の文体で書かれている作品だから短時間ですぐ読める。読んでみるといいよ。
ところでね、鷗外の短編小説に『普請中』って作品がある。明治42年に発表された。主人公は「渡辺参事官」。『舞姫』の太田豊太郎の「その後」を書いたような作品でね、ドイツにいたころ交際した女性が渡辺を訪ねてきて、「精養軒ホテル」で夕食をともにする、という話。その中に「ホテル愛宕館」と思われるホテルも登場する。短編だし、『舞姫』のような文体ではなく、いまの普通の文体で書かれている作品だから短時間ですぐ読める。読んでみるといいよ。
※なお、文中、引用の『舞姫』本文は、原則として、大正4年12月23日、千章館発行の『塵泥』(国文学研究資料館発行の復刻本『塵泥』)による。
⇒「セイゴンの夜④「『舞姫』文中の漢字、熟語の訓(よ)み方」」へ続く。



