セイゴンの夜④「『舞姫』文中の漢字、熟語の訓(よ)み方」
「五年前の事なりしか」

『舞姫』文中の漢字、熟語の訓(よ)み方が簡単、単純じゃない。
たとえば「中等室の卓のほとり」の「卓:つくえ」。「熾熱灯の光の晴れがましきも徒なり」の「徒:いたづら」。「骨牌仲間」の「骨牌:かるた」。「平生の望」の「平生:ひごろ」。「さらぬも尋常の動植金石」の「尋常:よのつね」。「こたびは途に上りしとき」の「途:みち」。そしてここの「五年前の事なりしが」の「五年:いつとせ」、etc.
「どうして「五年」は、「ごねん」ではなく「いつとせ」なの?」
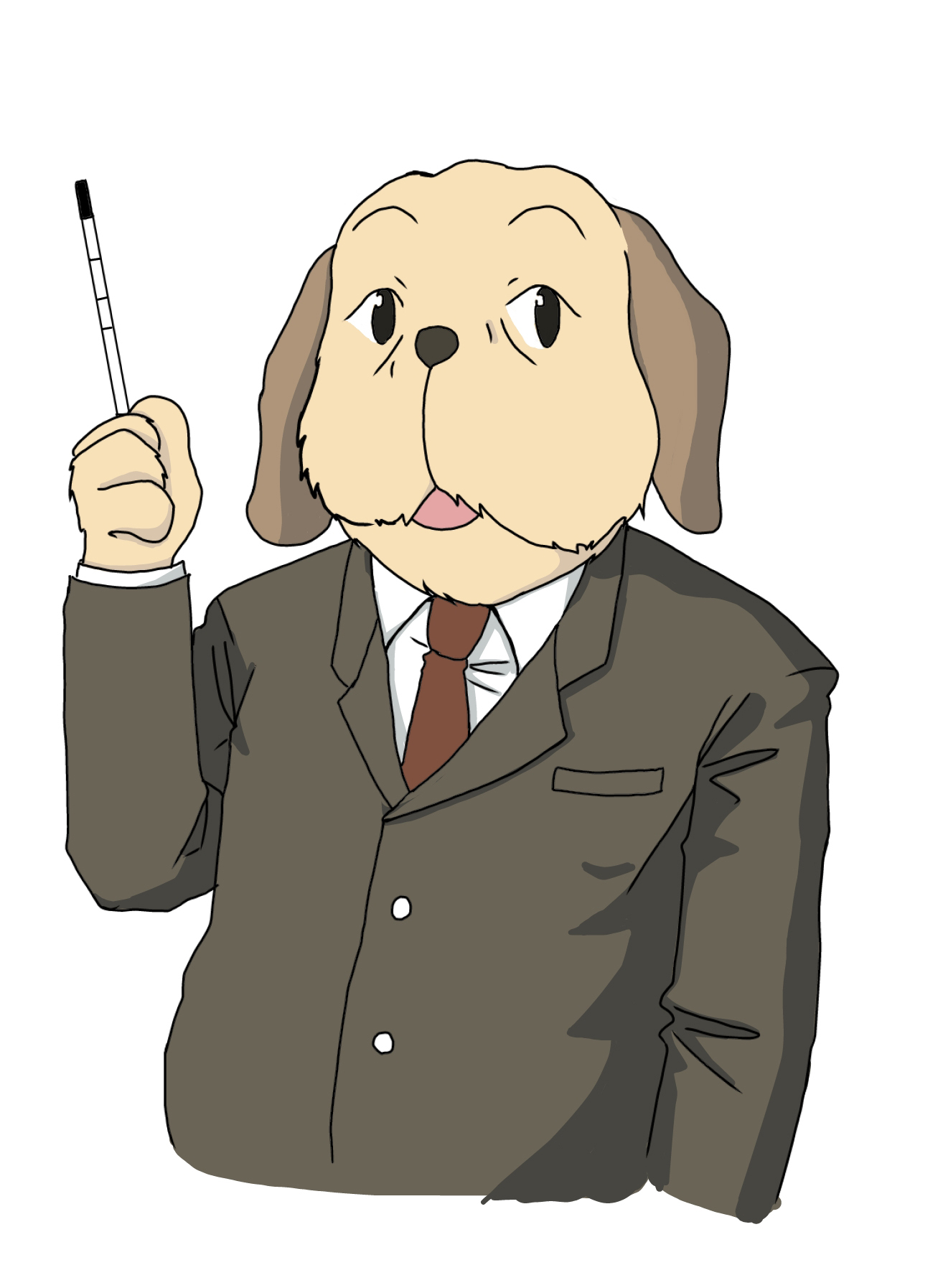 なぜかというと、作品のイントロ部分の直後に主人公の履歴を説明した部分がある。そのなかに「楽しき年を送ること三とせばかり」とある。だから、それから少し後の、ドイツ留学時代を描いた「かくて三年ばかりは夢の如くにたちしが」の「三年」も、作品の訓の整合性を持たせるためにも「みとせ」と訓まなくてはならない。とすれば、必然的に「五年」も「いつとせ」と訓むということになる、というワケ。
なぜかというと、作品のイントロ部分の直後に主人公の履歴を説明した部分がある。そのなかに「楽しき年を送ること三とせばかり」とある。だから、それから少し後の、ドイツ留学時代を描いた「かくて三年ばかりは夢の如くにたちしが」の「三年」も、作品の訓の整合性を持たせるためにも「みとせ」と訓まなくてはならない。とすれば、必然的に「五年」も「いつとせ」と訓むということになる、というワケ。
—— ところが、この「五年」がね、クセモノなんだよ。というのはさ、次のような次第。
いま主人公は「セイゴンの港」に碇泊中の船室にいて、この『舞姫』に描かれた「手記」を書いている。とすると、「五年前の事なりしが、平生の望足りて、洋行の官命を蒙り、このセイゴンの港まで来し頃は、」の「洋行の官命を蒙り、このセイゴンの港まで来」たのはいつだったのか、ということになる。
この問題を解決するキーポイントになるのは、作品後半部の初めに書かれている、「明治廿一年の冬は来にけり」にある。物語の展開の先取りになってしまう(『「序」にかえて』にも少し書いた)けれども、I am sorry。
|
東大法学部を首席卒業して「某省」に就職した豊太郎は、「官長」の絶大な信頼のもとに、三年後、ドイツ留学を命じられ、「我名を成さむも、我家を興さむも、今ぞとおもふ心の勇み立ちて」、「模糊たる功名の念と、検束に慣れたる勉強力とを持ちて」、勇躍ベルリンにやって来た。ところが三年ほど経って、彼は当初の目的と官長の期待から外れた道を歩き始める。そのころ、「エリス」という名の貧しい少女と知り合い、二人は内縁関係を結ぶ。そのことが官長に知れ、豊太郎は免職処分を受ける。ピンチに陥り、悩んでいた明治21年の初冬、天方大臣がベルリンにやってくる。旧友の相沢が大臣秘書官として同行、彼の援助で大臣の知遇を得た豊太郎は、その年の12月にロシアに向かう大臣に通訳として随行し、翌年、大臣の勧めによって、妊娠中のエリスをベルリンに残し、単身日本に帰国する。その途上、セイゴンの港で手記を書いている、 |
—— という展開。
だとするなら、明治22年を起点として、「五年」という歳月を遡れば、「五年前」は必然的に明治17年、ということになる。つまり、豊太郎が官長の命令を受けてドイツ留学の旅に発ったのは、明治17年ということになるわけだ。つまり、鷗外がドイツ留学の度に発ったのと同じ年ということになる。この年6月、日本鉄道の上野・高崎間が開通し、記念式典が行われた上野駅に「白熱電灯」24個が点灯された。日本における「電灯」の記念すべき幕開けであった。
が、ことはそんなに単純ではない。というのは、現在と違って明治のころは、「足掛け」という時間計算方式があった。たとえばある年の12月から翌々年の1月までの期間は、「足掛け」計算方式でいうと「三年」ということになる。そういう計算方式は、おそらく終戦前までごく普通に採用され一般に通用していた計算方式であった。その対立概念が「満Ο年」「まるΟ年」という言い方で、現在は「満」「まる」計算方式が一般的だ。
それと同じように、人の年齢の数え方も、現在は「満Ο歳」という計算方式が一般的だが、戦前は(もちろん明治のころも)「数えΟ歳」という表示方式が一般的だった。そしてそういう年齢の数え方、表示方式は鷗外もそれに拠っている。『自紀材料』という鷗外自身が書いた履歴書がそうなっている。「数え」という年齢計算方式の考え方は、人間が母親の胎内に宿ったとき、つまり人間としての生命を受けたときを起点として、受胎から出生までの期間を概ね一年と考えた計算方式で、生まれ月が12月であっても生まれた年が1歳で、翌年1月1日はその人の年齢は「2歳」ということになる。
そういう、明治期の一般的な歳月計算方式に従えば、「五年前」は、明治18年ということになる。日本に内閣制度が発足し、初代内閣総理大臣として伊藤博文が就任した年である(12月22日)。
「満」か「足掛け」か。『舞姫』文中には、豊太郎が大学を卒業して母親を故郷から東京に呼び「楽しき年を送ること三とせばかり」という記述もある。ドイツ留学後の描写のなかに「かくて三年ばかりは夢の如くにたちしが」という記述もある。同箇所には「今二十五歳になりて」という記述もある。「三年」という歳月は極端に言えば「満一年余り」ということもあり得る。「二十五歳」という年齢を「数え年齢」と考えれば、ほんとうは「満二十四歳」かもしれない。それら「五年」「三年」「二十五歳」をどう考えるかによって、豊太郎の「年表」に顕著な「誤差」が生ずる。学校の授業ではこんな話はたぶんなかろう。
—— 正解はずっと後で説明しよう。楽しみに待っていてくれたまへ。
「平生の望足りて、洋行の官命を蒙り」
太田豊太郎がいつごろ「洋行の志」を持ったかは分からない。「平生の望」とあるからあるいは大学在学中にその志が芽生えていたのかもしれない。しかし、かりにそうであってもそうでなかったとしても、彼は国家のお金で洋行できる(官費留学)最有力の候補者の一人であったはずだ。なぜなら彼はおそらく東京大学法学部の主席卒業者だから。ところが、彼の「洋行」実現までに「三年ばかり」かかっている。

「どうしてそんなにかかったの?」
—— そのあたりのことについて、当時の「洋行事情」について少しだけ話しておこう。
|
幕末から明治にかけて、海外に赴いた人は相当数いたにはいた。ただそうはいうものの、現在とは比較にならない。その理由は政治的事情、経済的事情、社会的事情等いろいろあっただろう。そうしたなか、さまざまな目的をもって海外に渡航した人たちは、ごく限られた人たちだったはずだ。 たとえば、石附実先生の研究によれば、明治11年から15年までの各年度、官費留学者数は100人にも満たない。多い年で83人、少ない年で56人である。その数字は、陸軍省、海軍省、文部省、司法省、開拓使、工部省の合計数字である。陸軍省が最も多く、次いで文部省の官費留学者が多かった。豊太郎の所属先とも考えられる司法省は、五年間で23人、明治15年はわずか2人だ。文部省からの留学派遣者数も豊太郎の洋行のころには毎年5人に満たない。 当然その選考基準は厳格で、鷗外の場合は卒業成績3番以内が条件。彼はすでにここでエントリーから洩れた。それでも鷗外がドイツに留学できたのは、文部省枠から陸軍省枠に期待変更したことと、上司の強力なバックアップがあったからだ。 |
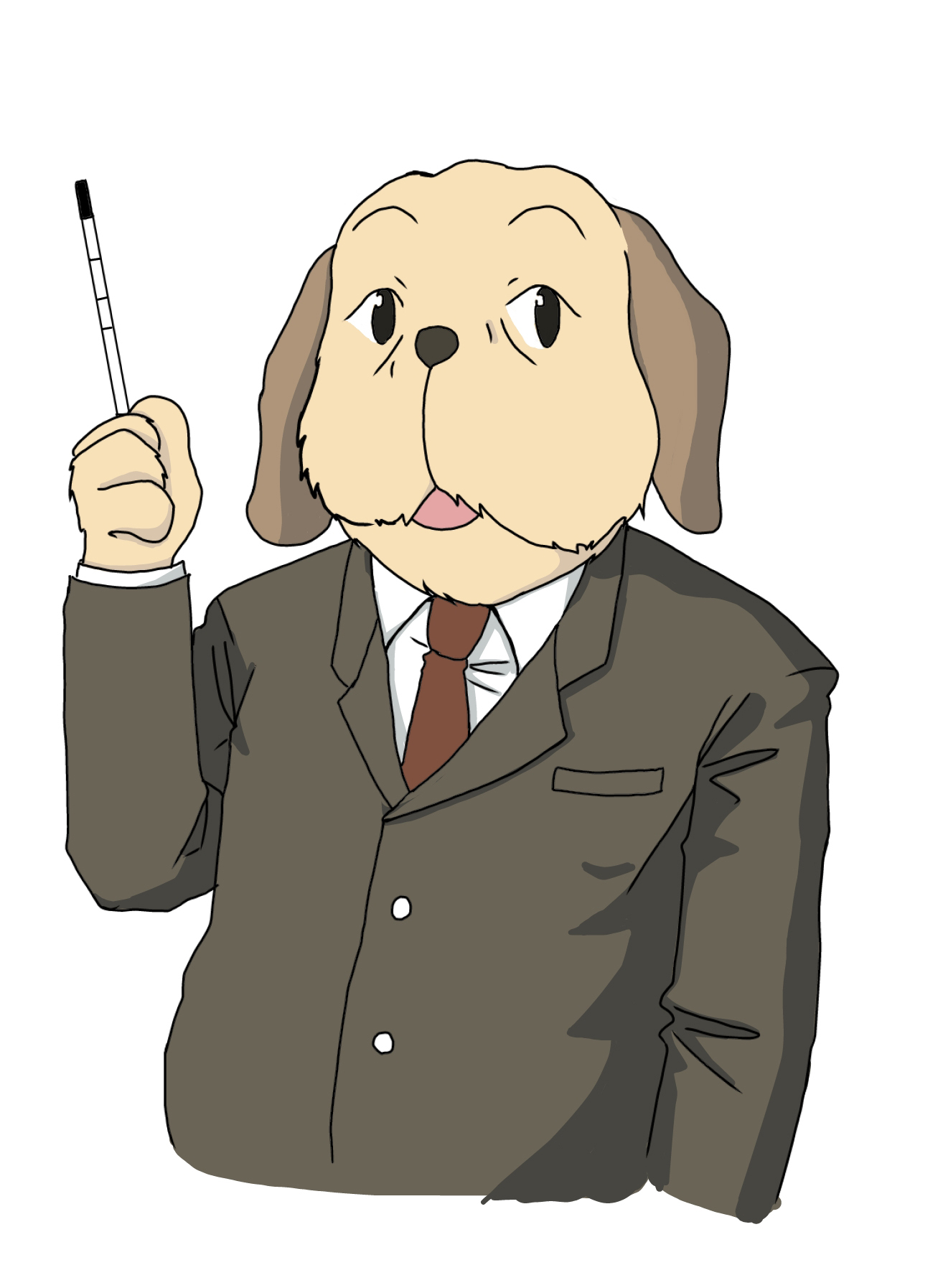
豊太郎の場合、卒業時点で文部省枠の官費留学のエントリー条件を満たしていたと思われるのに、なぜ彼は内務省または司法省に就職したのか。しかし結果として彼はそれが幸いした。豊太郎の能力を高く評価してくれる上司に巡り会えたことだ。そして彼はいつの日にか天皇に拝謁し、両肩にずっしりと「国家」を背負って横浜を出航したのだ。「洋行」とは、ただ「海外渡航」するというだけのことではない。それは文字どおり、東洋の弱小国日本という「国家への献身」を意味するものであった。豊太郎の背負った責任は、決して軽いものではなかったはずである。
※なお、文中、引用の『舞姫』本文は、原則として、大正4年12月23日、千章館発行の『塵泥』(国文学研究資料館発行の復刻本『塵泥』)による。
⇒「セイゴンの夜⑤「青年 太田豊太郎の一断面」」へ続く。



