セイゴンの夜⑦「ブリンヂイシイの港を出でてより」
—— 次のParagraphに行こう。
ああ、ブリンヂイシイの港を出でてより、はや二十日余りを経ぬ。世の常ならば生面の客にさへ交はりを結びて、旅の憂さを慰め合ふが航海の習ひなるに、微恙にことよせて房の内にのみ籠もりて、同行の人々にも物言ふことの少なきは、人知らぬ恨みに頭のみ悩ましたればなり。この恨みは初め一抹の雲のごとく我が心をかすめて、瑞西の山色をも見せず、伊太利の古蹟にも心をとどめさせず、中頃は世をいとひ、身をはかなみて、腸日ごとに九回すともいふべき惨痛を我に負はせ、今は心の奥に凝り固まりて、一点の翳とのみなりたれど、文読むごとに、物見るごとに、鏡に映る影、声に応ずる響きのごとく、限りなき懐旧の情を呼び起こして、幾度となく我が心を苦しむ。ああ、いかにしてかこの恨みを銷せん。もし外の恨みなりせば、詩に詠じ歌によめる後は心地すがすがしくもなりなん。これのみは余りに深く我が心に彫りつけられたれば、さはあらじと思へど、今宵は辺りに人もなし、房奴の来て電気線の鍵をひねるにはなほ程もあるべければ、いで、その概略を文につづりてみん。

ブリンヂイシイからセイゴンまで「二十日余り」って、どういうこと?
「ああ、ブリンヂイシイの港を出でてより、はや二十日余りを経ぬ。」については、第2講に書いた。

—— ブリンヂイシイは、細長いブーツのような形をしたイタリア半島の、カカトの位置付近にある港じゃよ。
|
鷗外自身は帰途ブリンヂイシイで乗船したわけじゃない。ベルリンを発ってロンドン、パリ経由、マルセーユでフランス船「亞瓦(Ava)」号に搭乗した。7月29日にマルセーユを出航し、8月3日にエジプトのアレクサンドリアに寄港している。とすれば、マルセーユ~ブリンヂイシイの就航所要日数は約2日。そうすると鷗外の帰途を参考にすれば、ブリンヂイシイ~セイゴンは就航日数25日か。船は「亞瓦(Ava)」号と同じルートだったと思う。スエズ運河~コロンボ~シンガポール~セイゴン。『舞姫』本文の「二十日余り」という日数計算が極めて正確なものであることが納得できるべ。 |
〇ベルリンからブリンヂイシイまではどういうルートか。
すぐ後方に「瑞西」「伊太利」とあるから、天方大臣一行は汽車で南下したのでござろう。その間約2日ほどかな。
〇同室の人との人間関係
ごく常識的に考えれば、豊太郎のセイゴン碇泊は2月下旬のことだったように思うが、その間豊太郎の船中での様子はどんなふうだったのかね。
『舞姫』本文によれば、「微恙にことよせて房の内にのみ籠もりて、同行の人々にも物言ふことの少なき」航海生活であったというけれど。第2講に参考として書いたように、もし豊太郎の「房」が六人部屋だったとするなら、同室のあとの五人との人間関係はどんなふうだったんだろう。
|
彼は「微恙にことよせ」ていたということだが、「微恙」とは軽度の病のことだから、今流にいえば「(精神的ストレスによる)体調不良」ということじゃないだろうか。一日二日の体調不良、たとえば船酔いというようなことであるなら、同室の人々も豊太郎に対してそんなに気を遣うこともないかもしれんが、しかし豊太郎の場合はもはや三週間もの長期間にわたっての体調不良だぜ。 しかもだよ。豊太郎が、日本に帰国するにあたっていかに突然大臣随行団に加わった人間だとはいえ、「人々」は、豊太郎という人がどのような人間であるかを全く知らないわけじゃない。なぜなら、豊太郎は、明治21年の暮れ一ヶ月、大臣の臨時随行員として、正式な随行員を差し置いて、ロシアで同国の要人と天方大臣との間に立って「通訳」として大車輪の活躍をしている人だよ。ふつうサ、こういう特別待遇の格差が、両者の間によろしくない感情を起こすのは、古今東西よくありがちなことじゃない? 『源氏物語』冒頭文の、桐壺更衣に対する、他の女御や更衣たちの陰湿な「いじめ」もそうだったしサ。人間のJealousyは時と場合を選ばないんだよ。豊太郎自身だって、彼はただまじめに暮らしていたのに、他の留学仲間から「あいつ、オレらと一緒にビールも飲まんし、ビリヤードも行かん。エラそうじゃんか」って妬まれたじゃないですか。豊太郎という男、ロシア出張中彼は他の随行員を尻目に、「肩で風切る」活躍ぶりだったんじゃないのかな。そこを妬まれた可能性はじゅうぶんあり得ると思うよ。 そういう人がサ、ほとんどベッドから離れることもなく、寡黙[かもく=だんまり]を貫いているというんだよ。それもサ、「世の常ならば生面(=初対面)の客にさへ交はりを結びて、旅の憂さを慰め合ふが航海の習」だということが分かっていての寡黙でしょ。どう考えたって、普通とはとうてい思えないよね。その寡黙の理由が「人知らぬ恨みに頭のみ悩ましたればなり」ということだとは、豊太郎自身の説明だ。なんかあるんじゃないか、とはだれだってそう思うよね。 |
で、以下はその「人知らぬ恨」の概略説明。次のParagraph以降、つまり、豊太郎の「手記」の部分は、その「人知らぬ恨」の詳細な説明部分というワケ。

「人知らぬ恨」って、分かりやすく言うとどういうこと?
—— この「人知らぬ恨」の説明部分を図示すると次のとおり。

 まるで、『方丈記』の冒頭部分を見るような対句の多用による構文だね。
まるで、『方丈記』の冒頭部分を見るような対句の多用による構文だね。
—— 最初の対が「初め」「中頃」「今」と、時系列による対句となっていることはすぐ気がついたべ。
「初め」とは、下に「瑞西」「伊太利」とあるから、ベルリンを発ってブリンヂイシイに至るまでの汽車の旅の期間を指しているのでござろう。その間、豊太郎の意識には、周囲の景勝地も歴史的観光地も上らなかった。それは「この恨」がそういう方面に意識が向くのを妨害したからだという。豊太郎は汽車に揺られている間中、じいっと下を向いているとか目を閉じているとかして目を窓の外に向けることをしなかったんじゃない? 完全に心の余裕を失っている状態だよね。
「中頃」は、ブリンヂイシイからシンガポールあたりまでのおよそ三週間ぐらいの間のことだろうか。豊太郎は、社会を否定し自己を否定し、すっかり落ち込んで、自分にしか分からん極度の精神的苦痛を舐なめていた。「微恙にことよせて房の内にのみ籠もりて、同行の人々にも物言ふことの少」なかったのは、そのためだったんだよ。その「人知らぬ恨」が、具体的にどういうものだったのか。それを説明したのが、この「手記」、つまり『舞姫』という物語だと、まあ、こんなワケさ。
その、誰にも分からん、そして誰にも知られたくない「恨」が、「今」、つまりサイゴン港碇泊中の現在、もしくはシンガポールあたりからとも考えられようか、やや落ち着いてきたというのでござろう。
|
で、ここまでの文を見るとサ、「何が、どんなだ」という、主語+述語の構文になっていること、気がついた?。つまり、「この恨」という主語に対して述語(述部)の部分でそれを説明しているという構文。先の例文中、傍線を施した部分がその述語(述部)の部分だ。 その次の部分は、時系列としては「今」に属する説明部だが、最初に置かれた「この恨」という主語がこの部分までも及んでいるものと考えよう。つまり、主語「この恨」に対する述語(述部)は、「限りなき懐旧の情を呼び起こして」「幾度となく我が心を苦しむ」の両方だ。 こういう『舞姫』の構文の特徴については、おじいちゃんの『森鷗外『舞姫』の全貌 言語学的研究に基づく考察』(右文書院刊)に詳しく分析してあるから、大学に行ったら必ず読みたまへ。猛烈に勉強になるぜよ。 |
だけど、ここ数日は豊太郎の心も若干は落ち着いてきたとはいうものの、なにかにつけて過去を振り返り、それがまた、針で突き刺すような精神的苦痛を呼び起こす。そして、「これのみは余りに深く我が心に彫りつけられ」ていたというのだから、豊太郎の心の痛みも、そりゃあ半端じゃないぜ。
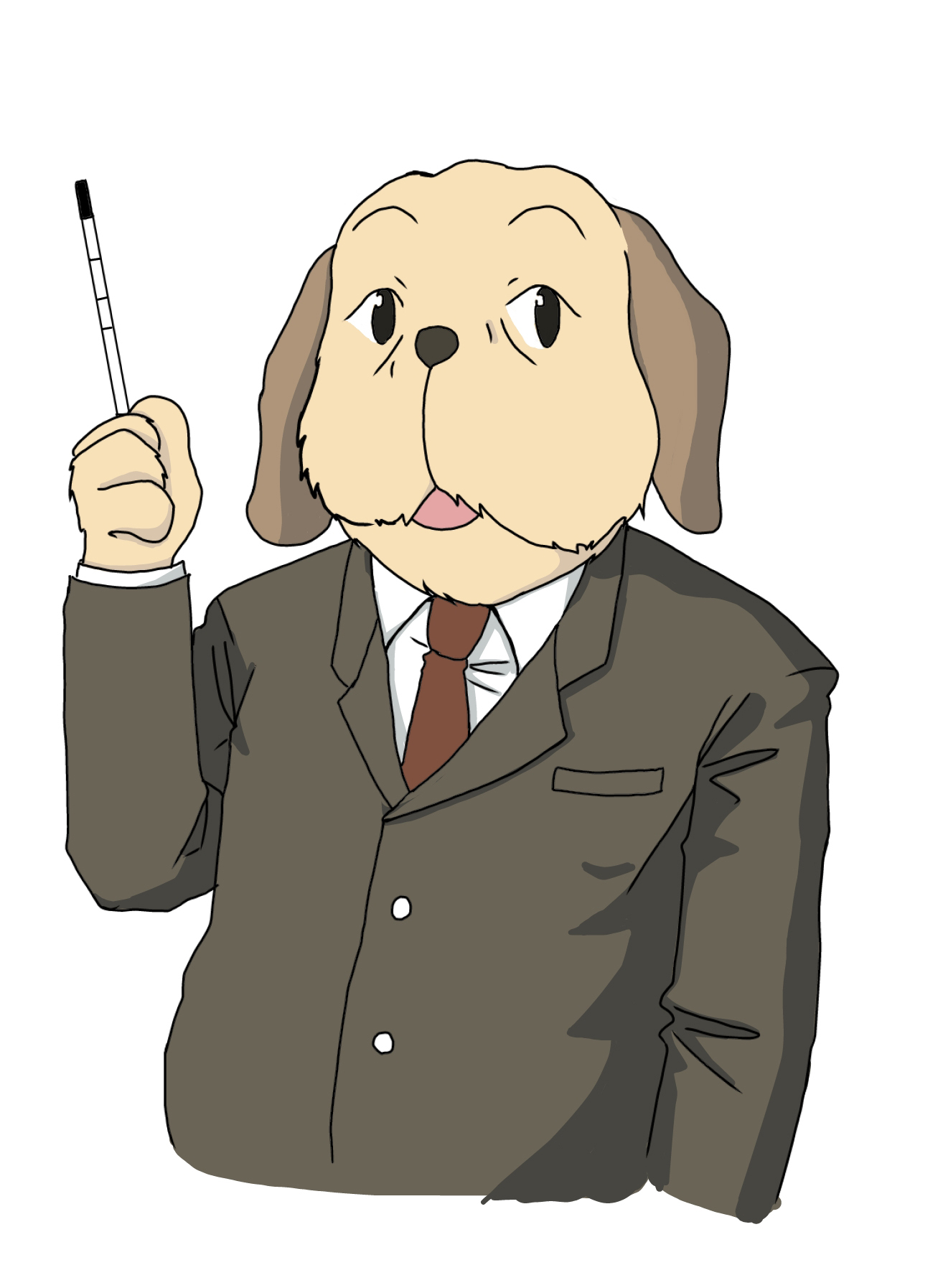 で、「この恨」について、こんなことを文章に綴ってみたって、自分の苦痛が消えるわけでもないし、心中のガス抜きになるわけでもないってことは分かっちゃいるけど、今夜は「房」にだれもおらんし、ともかくも書いてみるよ、って書いた手記が、『舞姫』って作品てワケよ。
で、「この恨」について、こんなことを文章に綴ってみたって、自分の苦痛が消えるわけでもないし、心中のガス抜きになるわけでもないってことは分かっちゃいるけど、今夜は「房」にだれもおらんし、ともかくも書いてみるよ、って書いた手記が、『舞姫』って作品てワケよ。
※文中、引用の『舞姫』本文は、明治書院『新 精選 現代文B』による。



