太田豊太郎の履歴書①「余は幼き頃より厳しき庭の訓へを受けし」
—— では、次に進もう。以後しばらくは、豊太郎の出生からベルリン留学までの簡単な経歴が書かれている。
余は幼き頃より厳しき庭の訓へを受けしかひに、父をば早く失ひつれど、学問の荒み衰ふることなく、旧藩の学館にありし日も、東京に出でて予備黌に通ひしときも、大学法学部に入りし後も、太田豊太郎といふ名はいつも一級の首に記されたりしに、一人子の我を力になして世を渡る母の心は慰みけらし。十九の歳には学士の称を受けて、大学の立ちてよりその頃までにまたなき名誉なりと人にも言はれ、某省に出仕して、故郷なる母を都に呼び迎へ、楽しき年を送ること三年ばかり、官長の覚え殊なりしかば、洋行して一課の事務を取り調べよとの命を受け、我が名を成さんも、我が家を興さんも、今ぞと思ふ心の勇み立ちて、五十を超えし母に別るるをもさまで悲しとは思はず、はるばると家を離れて伯林の都に来ぬ。

「豊太郎って、武士の出身?」
まずは「余は幼き頃より厳しき庭の訓へを受けしかひに、父をば早く失ひつれど」から。
このなかでキーワードは何かというと、「庭の訓」という言葉です。「庭の訓」とは「庭訓”ていきん”」と言ってね、もともとは『論語』(季氏第十六)にある話から出ている故事成語なんです。孔子が自分の子の鯉(り)に、「詩」(詩経)と「礼」(礼記)を学ぶ必要を説いたという話から、「家庭教育」の意味として使われる。この言葉は、能を大成した世阿弥も使っているそうだから、室町時代初期にはあった言葉でしょう。ただ江戸時代になって儒学が幕府の官学になると、武士道と結びついて、武家としての、親から子に伝える日常の倫理、という意味になったんじゃないだろうか。だから、「庭の訓」に注を付ければ「家庭教育」という言葉に置き換えることはできても、その意味は、現在における家庭教育とは自ずからその意味も重さも異なってくるべよ。
昔の家庭教育は今と違って厳しかったことは、おじいちゃんにも分かる。例えばね、おじいちゃんが育った家は田舎の農家だったけれど、そこには厳然として犯すべからざる「掟」があった。〈神仏を尊ぶ〉〈敷居は踏まない〉〈一家の主人(=父親)の座る場所(=横座よこざ)には女房子供は絶対に座ってはならない〉〈食事は一家そろって食べる〉〈食事の際、一家の主が箸をつける前は他の者は箸を付けてはならない〉〈ご飯は一粒残らずきれいに食べる〉〈食事中、話をしてはならない〉〈戸や障子の開け閉めは静かに〉〈家の中を走ってはならない〉〈言葉は相手にはっきり分かるように明瞭に発する〉〈長幼の序(=年齢の上下の順序)を守る〉〈親に〔口答え〕してはならない〉etc。
こういう「訓」はなにもおじいちゃんの家にだけあった「訓」じゃない。終戦直後の時代には、たいていどこの家庭にもあった「訓」だと思うよ。そういう「訓」をきちんと子に躾(しつ)けるのが親の責任だったワケよ。
鷗外の森家には「一種の気位(きぐらい)」があったそうです(『本家分家』)。また、鷗外もたぶん満五歳のころ「武士の儀式」を教えられたそうだ。
—— 『妄想(もうぞう)』という作品にこんな一説があるよ。
|
「西洋人は死を恐れないのは野蛮人の性質だと云(い)つてゐる。自分は西洋人の謂(い)ふ野蛮人といふものかも知れないと思ふ。さう思ふと同時に、小さい時二親(ふたおや)が、侍の家に生れたのだから、切腹といふことが出来なくてはならないと度々(たびたび)諭(さと)したことを思ひ出す。その時も肉体の痛みがあるだらうと思つて、其(その)痛みを忍ばなくてはなるまいと思つたことを思ひ出す。そしていよいよ所謂(いわゆる)野蛮人かも知れないと思ふ。併(しか)しその西洋人の見解が尤(もっと)もだと承服することは出来ない。」 |
おそらく豊太郎も父母から「切腹」の仕方を教わっていたにちがいあるまいよ。「切腹」とは、信義と忠誠に生きた時代の人々の、信義と忠誠の完結であり精算であり、自己または他者(必ずしも主君とは限らない)に対する引責の証だった。つまるところそれが「庭訓」というものだったと思う。だからいまの「家庭教育」とは自ずと意味が違うだろう。
鷗外の『独逸日記』に、鷗外がベルリン到着翌日、後に陸軍軍医のトップになった橋本綱常(つなつね)という人をホテルに訪ね、時代劇の一場面のように床に手をついて挨拶した。そしたら、橋本から「そんな挨拶はしないがよい」と戒められたと書いてある。床に手をついて頭を深く下げて挨拶するなんてことは、鷗外が幼児から躾けられた立ち居振る舞いの、ほんの「常識」「基本」であって、こういう生活上の守るべきルールは他にもいっぱいあったはずだ。たぶん太田家でも同じような厳格な「庭の訓」が行われていたことは間違いあんめ。
そして、大切なことは、そういう「庭の訓」が、豊太郎の人格形成に与(あずか)って大なるものがあったはずだということにまなちゃんが気がついたら、それはもうおじいちゃんは、いくらでもまなちゃんに「褒美」を出さなくちゃならん。それくらいこの「庭の訓」という言葉は大切なキーワードなのよ。
そういう次第だから、豊太郎の出自が武士階級だったという推論はおそらく正論だろうと思うよ(異論の可能性もあるけれど、詳しくはおじいちゃんの『セピア色の明治』を読んでね)。
ところがさ、そういう「庭の訓」を豊太郎に躾けた父親は、豊太郎の幼時に亡くなったとだけあって、その人がどういう人だかは全く説明がない。亡くなったときこの父親もたぶんまだ若かっただろうとは推測できるけれども、太田の直系の人かどうかは分からん。そのことについてはまたいずれ話そう。

「旧藩の学館」って、江戸時代の藩校のことだよね。
太田豊太郎は、早く父を亡くしたという。その父の厳格な「庭の訓」のおかげで、学問に対する高い意欲はその後成人するまで失われることはなかった。その部分、「旧藩の学館にありし日も、東京に出でて予備黌に通ひしときも、大学法学部に入りし後も」は、対句として「太田豊太郎といふ名はいつも一級の首に記されたりしに」に係っていく文構造だ。つまり豊太郎は自己紹介として、自分はご幼少のみぎりから成人するまで一貫してトップを走り続けたと言っているワケだ。
この最初の「旧藩」が具体的にどこの藩か、その藩の「学館」はなんという学館であったかは明らかでない。しかしその「学館」が「旧藩」の「藩校」であることはまちがいない。その「藩校」で授業を受けている児童生徒のうち、豊太郎がとびっきりの超優秀者であったことは、もう少し後に「人の神童なりなど褒むるがうれしさに怠らず学びしときより」とあることによって分かろう。ただ、豊太郎のその「神童」ぶりがどのようであったか分からん。それで、参考までに作者鷗外の「神童」ぶりについて、二、三話しておこう。
鷗外は文久二(一八六二)年、島根県津和野に生まれた。現在の幼稚園年齢のころから漢学を始め、小学校二年ごろから藩校養老館で学問に励んだ。当時、鷗外を教えた先生が、「他の子供はなかなか覚えられないものを、林太郎は一回で覚えた」と言ったという。
一昨年(平成30年)の夏、今の小学校低学年のころに鷗外が筆写した『童蒙入学門』の写本が発見されたということが新聞に出でたこと、まなちゃんも覚えておろう。おじいちゃんがその新聞の写真の文章を読んで少し解釈してやったっぺ。
『童蒙入学門』は、江戸時代後期の国学者平田篤胤[あつたね]の著作。養老館では道徳のテキストとして使っていたという。それ、漢文で書かれていたよね。
—— どんな文章だったか、思い出して欲しいので、次にその冒頭の章を引用しておこう。
〇敬神章第一
凡 生 於 世 者 恒 当 尊ー敬 神。其 故 何 也。太 古 所 在 者 唯 神。有 神 而 有
物。則 是 日 月。星 辰。国 土。人 類 万 物。悉 無 非 之 神 之 所 生。是 故 須 毎
旦 拝 礼 而 思 酬 其 恩 頼 也。
鷗外の写本には訓点がついている。しかし当時の鷗外の実力からすれば、訓点はあってもなくてもよかったんじゃないのかな。もちろん文章の意味もちゃんと分かっていただろう。これくらいの漢文なら、鷗外は白文でたぶん読めたに違いない。いや、それだけじゃない、鷗外は同じころ、自分のお父さんからオランダ語を学んでいた。そして、その難解な文法書も自学していた。鷗外、恐るべし。
そんな鷗外だったから、幕末から明治にかけての啓蒙家、西周(にしあまね)、彼も津和野の人で鷗外の親戚筋に当たる先輩だが、津和野に里帰りしたとき、鷗外の神童ぶりを聞いて、明治の初年に自分が校長をやってた「沼津兵学校」に鷗外を連れて行こうとした。結果として鷗外は沼津に行くことはなかったが、当時、最新の近代教育を施していた学校に入学させようとしたのだから、鷗外という人が幼少のころからどれくらい優秀なすごい人であったかは、ほぼ想像がつくんじゃないか。
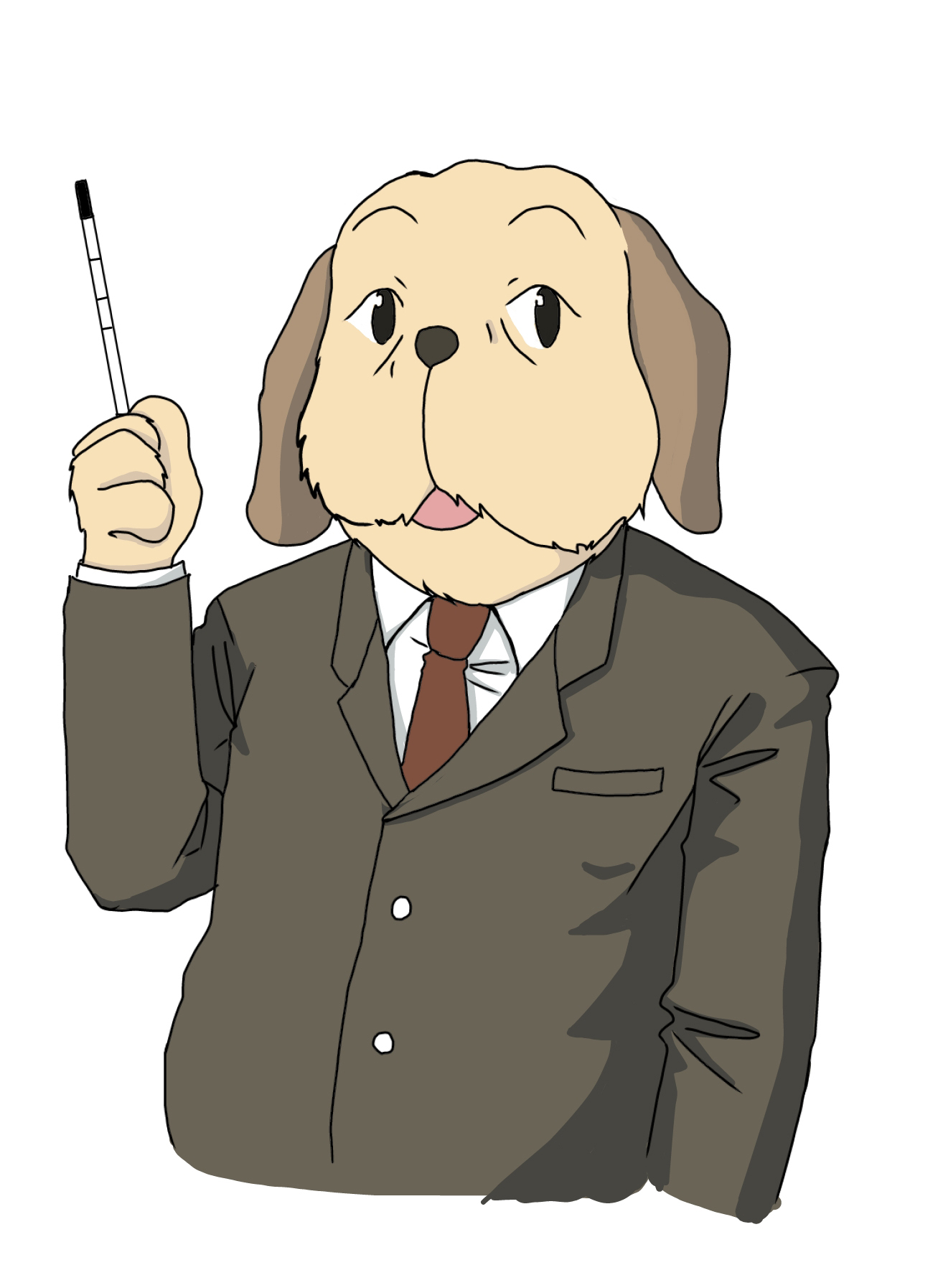 豊太郎が幼少のころ、藩校で何を学び、どの程度優秀であったかは分からん。じゃが、当時の各藩の藩校で教えていた教科科目を見れば、おじいちゃんの推測するところ、鷗外とほとんど同じくらいの「神童」ぶりだったことは間違いないと思うがの。
豊太郎が幼少のころ、藩校で何を学び、どの程度優秀であったかは分からん。じゃが、当時の各藩の藩校で教えていた教科科目を見れば、おじいちゃんの推測するところ、鷗外とほとんど同じくらいの「神童」ぶりだったことは間違いないと思うがの。
※文中、引用の『舞姫』本文は、明治書院『新 精選 現代文B』による。
⇒次回「太田豊太郎の履歴書②」



