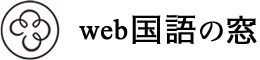評論文読解のキーワード「宗教」
1-2-2「宗教」
ここでは、主に「宗教」の本来の意味を考えていきます。
①宗教とは
ⅰ)「無宗教」という宗教
ほとんどの日本人が「自分は無宗教だ」といいます。
そのくせ、年末にキリストの生誕を祝い、年始に初詣でに行きます。
いやいや、あれは「イベント」だから、、、
しかし、海外から見ると、日本はどっぷり仏教国です。
日常使っている言葉にも、何気なくやっている生活習慣にも、仏教が染みついています。
なのに、「無宗教」とうそぶくのはどうしてでしょう。
少なくとも、私たちがこの世界で生きていけるのは、何らかの形で世界のあり方を了解しているからです。
本来の意味での「宗教」は、そうした世界のあり方を教えてくれるものであり、そのシンボルこそが「神」です。
「~教」とか「~宗」と名乗っているものだけが「宗教」ではありません。
むしろ、本来の「宗教」は、生活に根ざしているものであって、だからこそ、自分がその教えにしたがっていることすら意識されないものです。
ということは、「自分は無宗教だ」と思っている人は、まあいわば「無宗教」とでもいうべき宗教に染まっていて、でも、それが自分の生活と一体化しているせいで、自分が「無宗教」に属していることがわかっていないだけでしょう。
ちなみに、「無宗教」とは、さまざまな宗教行事に無節操に参加してもよい、多神教的な宗教のようです。
そういえば、神道も、仏教も多神教的です。
日本は風土的に自然が豊かですから、多神教がなじむのでしょう。
ⅱ)宗教というメガネ
宗教が世界のあり方を教えてくれるものだからこそ、宗教対立は深刻になりがちです。
赤い色眼鏡をかけた人と青い色眼鏡をかけた人では見える世界の色が違うはずです。
しかし、眼鏡をかけていることに互いが気づいていなかったら、自分の見えている世界こそ正しい世界の色だと思うでしょう。
宗教は世界を見る一種のメガネですから、宗教によって見えている世界は違います。
しかも、それが生活に溶け込んでいるわけですから、自分の見えている世界こそが正しいと思い込んでしまう。
お互いに見ているものが同じでありながら、見え方が違うわけで、なかなか話し合いも歩み寄りもしがたいのがわかるでしょう。
②神からの解放
ⅰ)世俗化
キリスト教の教えや教会は、中世ヨーロッパの《貧しさ》を支えてきましたが、豊かになっていくにしたがって、人々の意識や行動を縛るものになってきました。
そうした神の軛(くびき)から逃れることで、ヨーロッパは近代になったのです。
それを「神からの解放」といいます。
かっこよくいうと、「世俗化」とか「脱呪術化」といいます。
いずれも、宗教的でなくなるという意味です。
中世ヨーロッパの地図には、しばしば、エデンの園が書かれていたそうです。
しかし、世俗化の結果、地図からはエデンの園が消えてしまいました。
ただ、近代になって私たちは本当に宗教から逃れられたのか、というと、、、
それは違います。
ヨーロッパの人たちが、いくらキリスト教の影響から解放された、と思っていても、その言動はキリスト教の影響を色濃く受けています。
が、本人たちにはその自覚がありません。
最初に取り上げたように、多くの日本人も自分のことを「無宗教」だと思っています。
ⅱ)宗教に代わるもの
本来の宗教は、世界のあり方を教えてくれるものであって、人間がこの世界で生きていくために不可欠なものです。
にもかかわらず、それがなくてもどうにかなる、と思えるためには、宗教の本来の役割を肩代わりするものがなければならないでしょう。
かつて、世界の誕生は、宗教によって語られました。
今それを語っているのは、科学です。
「科学的に言えば」というフレーズが、しばしば「神の御言葉によれば」とダブって聞こえてくるのは、私だけでしょうか。

大前 誠司 編著
1,430円・四六判・328ページ