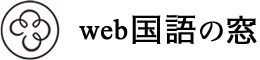評論文読解のキーワード「空間/時間」
1-2-10「空間/時間」
ここでは、「空間」と「時間」についてお話します。
①空間
ⅰ)客観的な時間~無限で均質~
数学で使う平面座標、よくxy座標などといっていますが、あれを誰が作ったか、知っていますか。
実は、デカルトです。
だから、あの平面座標はデカルト座標と呼ばれています。
デカルト座標では、必ず、原点と矢印、書きますよね。
原点は世界の出発点という意味ですが、その原点、どこにとってもいいはずです。
でもなんでそんなことが許されるかといえば、この世界が均質だからです。
Aという場所もBという場所も同じだから、Aに原点をとってもいいし、Bに原点をとってもいい、もちろん、君たちのノートのどこにとってもいい、というわけです。
一方、矢印は、世界が無限に広がっていることを示しています。
つまり、原点と矢印は、この世界が無限で均質だということを表しています。
ⅱ)主観的な空間~有限で意味に満ちている~
しかし、私たちにとっては必ずしもそうではありません。
たとえば、教室には、前と後ろがあります。
廊下側や窓側があります。
決して、教室は均質とはいえません。
もちろん、無限でもありません。
主観的には、空間は決して均質でも無限でもないのです。
それは、空間が、その中に暮らす人間とのかかわりのなかでさまざまな意味をもってしまうからです。
ⅲ)豊かさ?
だから、そうした人間とのかかわりを排除したところに客観的な空間は生まれてきます。
近代の大きな特徴は《切り離し》です。
空間から人間を切り離すところに、近代的な空間観が生まれてきます。
たとえば、先祖代々神の住まう場所として敬ってきた裏山をゴルフ場や産廃処理場にしてもかまわないのは、裏山が特別な場所ではなくただの山にすぎないからです。
むしろ、村を経済的に豊かにするのだから、効率的な空間利用といえるでしょう。
が、それが本当に《豊かさ》といえるのでしょうか。
②時間
ⅰ)主観的な時間~円環時間~
近代になって、時間も、直線的に流れる、均質で無限なものだと考えられるようになりました。
が、私たちにとっては必ずしもそうではありません。
朝昼晩という一日の巡り、春夏秋冬という一年の巡り、生まれては死んでいく人間の一生――時間は、始まりと終わりをもちながら、ぐるぐる回っているように思えます。
身近な者の死は、少なくとも命あるものの時間の有限性を実感させます。
大学受験の日、その合格発表日――特別な意味をもつ日はいくらでもあります。
主観的には、時間は決して均質でも無限でもないし、まっすぐ流れていないようです。
ⅱ)客観的な時間~直線時間~
それに、、、
近代以前、全世界で共通した時間などありませんでした。
寺や教会の鐘で時間を知ることはあったかもしれませんが、人々はまず、日の出、日の入りを基準にして生活を営み、村や町という単位でしか時間は共有されていませんでした。
時間は、村ごと、町ごとに違っていて、それでかまわなかったのです。
が、鉄道が村や町を結ぶようになると、そうはいきません。
交通の発達が、世界共通の時間を必要としたのです。
そう考えると、もともと時間というものは、人間の暮らしと一体化した、いわば内在的なものであったのかもしれません。
しかし、近代になると、時間は、人間の暮らしから切り離され、人間の外側に流れる外在的なものになります。
円環的ではなく、直線的に流れる、均質で無限な時間が、客観的な時間だと見なされるようになったのです。
ⅲ)豊かさ?
そこで求められるのは、時間効率、いわゆるタイパ(time performance)です。
現代人は時間に追われて暮らしています。
だからこそ、タイパを重視するのでしょうが、そのせいでよけいに時間に追われてしまう。
かぎられた時間の中でできるだけ多くのことを、という強迫観念に取り憑かれているようです。
今、人生100年時代といわれますが、平安時代の貴族の寿命は4~50歳だったそうです。
もし、時間が外在的で客観的に計れるものなら、今の方が2倍充実した人生を送れているはず。
が、実際にはどうでしょうか。
近代は《豊かさ》の時代です。
より多くのものを生産し、消費することがよいことだとされてきました。
が、より豊かになった現代は、そうした「量」よりも「質」を大切にし始めています。
タイパが空しいのは、結局、時間あたりの情報量の多さを求めているにすぎないからです。
空間を考えるにつけても、時間を考えるにつけても、現代において大切なのは「質」的な観点。
人間の暮らしと深く結びつけて語ることが必要なようです。

大前 誠司 編著
1,430円・四六判・328ページ