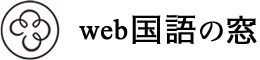評論文読解のキーワード「歴史」
1-2-14「歴史」
ここでは、「歴史」についてお話します。
①文化との関係
私たちの生の営みは、刻一刻と歴史に刻まれています。
「歴史」とは、過去だけでなく現在も未来も含めた〈人間の生の営み〉です。
文化も〈人間の生の営み〉ですが、文化がそれを空間的な広がりのなかで共時的にとらえるのに対して、歴史は時間の流れに沿って通時的にとらえます。
たとえば、1945年に第二次世界大戦が終結した、といいます。
これは、終戦という出来事を1945年という時間に位置づけているわけです。
②歴史主義
このように、さまざまなものごとを時間の流れのなかに位置づけてとらえることを歴史主義といいます。
日本より30年後れている、とか、10年進んでいる、といいますよね。
これは、何かを日本の時間の流れのなかに位置づけてとらえている表現です。
結果的に、歴史主義は、進歩史観や啓蒙主義と同じように、《進んでいる/後れている》というとらえ方になります。
詳しくは、「文化」の項で、ヨーロッパ文明中心主義を確認してください。
③storyとしての歴史
ⅰ)物語
英語の「history」は、「story」と語源的に同じです。
歴史は物語だというわけです。
「物語」とは〈人々に共有されている、何かを成り立たせるお話〉です。
つくりごとではあるけれど、人々の間で正しいものとして共有されている話。
共有されることで、人々の生を成り立たせ支えるものです。
その代表といえるのが、科学です。
科学が描く世界は、この世界をある側面から見た一つの姿にすぎません。
が、科学こそが現代の《豊かさ》を成り立たせているので、科学的なものの見方は正しいこととして共有され、私たちの生を支えています。
ⅱ)強者の歴史
さて、歴史です。
正確にいえば、歴史は文献資料に基づくものなので、文献資料のない時代を「先史時代」と呼び、「歴史時代」と区別されます。
そもそも、文字を残すことはその他大勢にはできないことです。
ということは、歴史は常に強者の物語です。
しかも、その文字資料を読み解き、解釈するのも、後の世の強者です。
その意味で、歴史は、ただの物語ではなく、その時代の強者を正当化する物語になります。
日本史の教科書では、朝廷を中心として歴史が記述されています。
「日本」史といいながら、日本列島全体の歴史ではありません。
もちろん、文献資料が残っているのが地域的に偏っているからそうなっているのでしょう。
が、たとえば、江戸幕府と呼ばれる徳川政権が、いつから「幕府」と呼ばれるようになったか、知っていますか。
江戸時代末期、徳川政権を倒すための対抗勢力として薩長に担がれた朝廷が、「徳川家は自分の子分だ」というために言い出しただけです。
が、それが今の歴史の教科書で歴史用語として堂々と使われています。
それがまちがいだ、という指摘をしているわけではありません。
この場合、歴史は歴史の勝者である明治政府から見た物語だ、といっているだけです。
ⅲ)いくら物語といっても、、、
歴史の教科書は、時代とともに内容が変わっています。
たとえば、日本史から江戸時代の身分制度だとされていた士農工商が消えています。
鎖国もそろそろ消えそうです。
そもそも、オランダや中国と国交をもちながら、鎖国っておかしいと思いませんか。
歴史の内容が変わるのは、新たな資料も含めて、歴史を読み替えたからです。
歴史は、物語だからこそ読み替えることも可能です。
新たな資料があればそれを取り込むべきですし、より説得力があるなら新しい物語を受け入れるべきでしょう。
しかし、そこで大事なのは、資料を都合よく取捨選択してはならないということです。
歴史修正主義と呼ばれるものがあります。
たとえば、ホロコーストや南京大虐殺はなかったという話。
いずれも、大半の歴史学者にとって、すでに決着のついている話題です。
さまざまな資料が残っており、疑いの余地がない出来事です 。1)
が、いまだになかったと騒いでいる人たちがいる。
そうしたつけ入る隙があるのも、歴史が物語だからです。
歴史を強者のものだけにしないためにも、素人からの逆襲はナシではないでしょう。
が、歴史修正主義の問題点は、偏狭な愛国心やナショナリズムと結びついて、自分に都合のいい物語を語ることです。
歴史修正主義は、自民族中心主義を母にもちます。
だから、日本では、「南京大虐殺はなかった」という声は上がりますが、「ホロコーストはなかった」とはいわれません。
修正したいのは、あくまでも自国の都合の悪い歴史だからです。
物語である歴史が、国家としてのあり方、ナショナル・アイデンティティと深くかかわっていること。
それが、国民としての私たち自身のアイデンティティと深くかかわっていること。
そのような歴史の立ち位置が、自国の歴史を少しでも美化したいという歴史修正主義を生み出すのでしょう。
ⅳ)弱者の物語
現在では、多くの市井の人が文献資料を残しています。
いや、文字だけでなく、映像や音声、メモリやクラウド上の記録、さらに人やものの記憶まで、膨大な資料があります。
そうした時代にあって、歴史を強者だけのものとしてとらえるのは間違っているかもしれません。
たとえば、2002年サッカーワールドカップ決勝。
その日、決勝の会場から数キロ離れた横浜の住宅街では、そんな熱狂と無関係に日常をすごす人たちがたくさんいました。
それもまた歴史の一コマのはずです。
こうした弱者の歴史をどう編み上げていくか、もまた、現代の私たちの課題でしょうか。

大前 誠司 編著
1,430円・四六判・328ページ