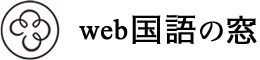評論文読解のキーワード「古代(ヨーロッパ)」
1-1-1 古代(ヨーロッパ)
今回は、「古代」です。
古代というと、普通、古代ギリシアと古代ローマを指します。
古代ローマは、社会制度の分野で近代に大きな影響を与えています。
たとえば、現在の日本の民法は、実は、ローマ法がベースになっています。
が、現代文にはほとんど出てきませんので、ここでは古代ギリシアについてお話しします。
①〈豊かさ〉の時代?
 さて、質問です。
さて、質問です。
右の地図のどこが「ヨーロッパ」でしょうか。
古代にヨーロッパと呼ばれた地域は、現在と地理的に違います。
世界史でヨーロッパ史をやった人。そういえば、古代では地中海沿岸しか出てこなかったでしょ。
古代ヨーロッパは、地中海の、温暖で、豊かな自然と、奴隷制度に支えられて、市民が《豊かさ》を享受した時代でした。
人間、暇になると、暇つぶしが必要になります。
それが娯楽や芸術です。
でも、あまりに暇になると、どうなりますか。
たとえば、風邪で寝込んで、やることもなく、何日もただただ横になっているとき。
それまでまったく気にもしなかった、部屋のカーテンの汚れ具合が気になったり、自分や世の中のあり方、さらには、そもそも人間とは、なんて考え始めてしまいます。
古代ギリシアの市民たちは、生産活動全般を奴隷に任せて暇になった結果、娯楽や芸術が発達し、さらには、当たり前であるはずの「世界」という存在に目を向けるようになりました。
それが、近代に大きな影響を与える「懐疑」と「原理」という2つの考えを生み出したのです。
②懐疑
まず、「懐疑」。
〈当たり前を疑うこと〉です。
たとえば、目の前のものを「机」と呼ぶのはどうしてでしょう?
大学に行くことが自分の人生に役立つと思っているのはどうしてでしょう?
自分にとって「当たり前」だと思っていることが、本当に正しいのかどうか、考えたことがありますか。
それを疑うことを「懐疑」といいます。
こうした知的な態度のことをギリシア語で「エピステーメ」というのですが、この「エピステーメ」がラテン語、フランス語、英語と伝わって、「サイエンス」=科学になりました。
だから、科学とは、そもそも、目の前に広がる世界を疑い、探求することで得られる知を意味する言葉です。
③原理
そして、「原理」。
原理とは、〈世界を作り上げている根本的な何か〉のことです。
でも、目の前のものを見えているとおりに見ているかぎり、原理を見いだすのは不可能です。
現在の科学の考え方に従えば、目の前にある「机」も、蛇口から流れ出てくる「水」も原子からできています。
それを見いだすには、まず、「机」を「机」のまま捉えてはダメなはずです。「水」を「水」のまま捉えてはダメなはずです。
見えているものを懐疑し、「机」や「水」を作り出している根本的なものを探求した結果、原子という発想にたどりつきます。
そのように考えた一人がデモクリトスです。
この世界は「アトム」からできている、と考えました。
ピタゴラスは、この世界の根源を「数」だと考えました。
彼は、三平方の定理で有名ですが、実は「数」を信奉する宗教団体の教祖さまだった、ということはあまり知られていません。
たしかに、世界の根源、って、神様っぽいですよね。
歴史的には、この「原理」という考え方が、キリスト教を生み出し、科学の根本を作り上げました。
➃形而上/形而下
面倒くさい言葉ですが、知っておいた方がいい言葉が「形而上/形而下」です。
これは、「原理」から生まれます。
原理とは、この世界を成り立たせている根本的なもの、でした。
でも、それって見えないですよね?
たとえば、目の前の机を見るとき、目に見えているのは「机」であって、それが「原子」でできているというのは、頭でしかわかりません。
つまり、「原理」を前提にすると、目に見えている形而下と、頭でしか捉えることができない形而上に、世界は分かれてしまうわけです。
形而下は、もともと、ギリシア語で「physis(ピュシス)」。
「自然」を意味する言葉で、形があって、目に見える世界のことです。
英語で「物理学」は「physics」でしたよね。
それを思い出すと、形而下が〈物の世界。形の世界〉だとわかりやすいでしょう。
形而上は、ギリシャ語で「metaphysis」。
「meta」とは越えるという意味なので、形而上は〈形を越えた世界。頭で捉えた観念の世界〉だとわかります。
この形而上/形而下は、この後、中世のキリスト教的世界観、近代のデカルト二元論を生み出していきます。
ヨーロッパにおける世界観の基本的な枠組みですので、面倒くさそうな言葉ですが、覚えてください。
動画を見る