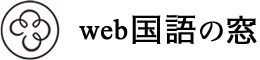評論文読解のキーワード「近代」
1-2-9a「近代」
ここでは、「近代」についてお話します。
「近代」ヨーロッパについては、「時代区分」の章で取り上げているので、こちらでは、 《豊かさ》を手に入れることで、人間や自然の関係がどうなるのか、考えていきましょう。
①《貧しさ》
貧しいとは、生活するための物がなかなか足りていない、ということです。
だから、人々はわずかな物を分けあい、助け合いながら生きていました。
仲間はずれにすることを「村八分」といいますが、村人が生きていくために、村の和を乱す者はそうするしかなかったわけです。
《貧しさ》のなかでは「伝統」が大切にされます。
それはどうしてでしょうか。
人々は、《貧しさ》のなかでも、いや貧しいからこそ、さまざまな生き抜くための努力をしてきたことでしょう。
しかし、そうした努力がなかなか報われない状況こそ《貧しさ》というのであり、そこでの不用意な失敗は死も意味します。
現代の「貧困」問題でも、「貧困」を抜け出せないのは、その人の努力が足りないからだ、といわれることがあります。
しかし、新しいことに気楽にチャレンジできるのは、まずその元手があること、そして、もし失敗してもどうにかなる余裕があるときです。
そうした余裕がない人は、失敗を恐れて、こうやればいい、とこれまで言われてきたとおりのことをやることになります。
それが伝統と呼ばれるものです。
伝統は、昔ながらのただの教えではありません。
《貧しさ》を実際に生き抜いてきた人々の経験や知恵です。
だから、そうした知識や知恵を持つお年寄りが尊重されます。
ところで、グラミン銀行って聞いたことがありますか。
貧しい人たちを対象に、小額の融資を行うバングラデシュの銀行です。
創始者のムハマド・ユヌスが74年に42家族に総額27ドル貸したことから始まった試みです。
1ドル150円で計算しても、1家族あたり100円です。
そのわずかなお金が、《貧しさ》から抜け出すきっかけになりうるのです。
逆にいうと、その100円をもたない人たちに対して、チャレンジ精神がないと非難できるでしょうか。
ちなみに、グラミン銀行は、、2006年にノーベル平和賞を取りました。
②《豊かさ》
ⅰ)自由→進歩→進歩史観
貧しいからこそ、人々は、他の人や物と深くつながっていました。
が、それは、周りの人間や物との関係性に囚われている、ということでもあります。
《豊かさ》は、こうした柵(しがらみ)から人々を解放します。
簡単な話です。
もし、消しゴムを1個しかもっていなかったら、その消しゴムを大事に使うしかない。
なくしてしまったときのために、隣の人との関係も大事にしないといけません。
でも、消しゴムを何個ももっていたら、1個1個の扱いは雑でかまわない。
隣の人に借りる必要もないので、お隣との人間関係は、その分どうでもよくなります。
物がたくさんあると、物の扱いも人間関係も適当でいい。
《豊かさ》は、人々を「自由」にするのです。
だから、伝統からも自由になりました。
これまでのやり方を否定することで、より新しいことにチャレンジし、より豊かになっていきました。
《豊かさ》は好循環を生み出します。
新しいことをやる元手がある。
だから、新しいチャレンジができる。
もし失敗してもやり直せる余裕がある。
成功すれば、より豊かになった成功体験が次のチャレンジを促す。
そうしたチャレンジ精神こそ主体性と呼ばれるものであり、人間は主体性をもっているからこそ、進歩し続けていると考えられるようになりました。
これを進歩史観といいます。
この「進歩」を「成長」と読み替えたものが資本主義です。
ⅱ)若さ→記号性
いつの時代も、肉体的な衰えとしての「老い」はいやなものでしょう。
しかし、年をとるということは経験を重ね、生き抜く知恵を磨くということです。
《貧しさ》のなかでは、「若さ」はそうした経験や知恵を持たない未熟さでしかありませんでした。
ところが、《豊かさ》はより新しいことにチャレンジすることで生まれますので、《豊かさ》のなかでは、古いものは嫌われ、より新しいものが好まれます。
《貧しさ》のなかではお年寄りの知恵が尊重されていましたが、《豊かさ》のなかでは若いことが価値をもつようになりました。
たしかに、深夜のテレビCMでよく見かけるのは、女性向けの化粧品やサプリメント、男性向けの増毛剤、、、
「若さ」、いや「若く見えること」をめざしたものばかり。
現代の「若さ」は、「見た目」勝負のようです。
シミソバカスがないこと、髪の毛がたくさんあること――それが「若さ」の記号なのでしょう。
昔から、第一印象が大事、といわれてきました。
人間関係が希薄な現代は、その人物の内面ではなく外面で判断するしかないのかもしれません。
が、若く見えることがその人の価値を決めてしまうような風潮はどうか、と思うのは年寄りのひがみというものでしょうか。
1-2-9b「近代」
「近代」の後半です。
《豊かさ》について引き続きお話します。
②《豊かさ》
ⅲ)《切り離し》→アイデンティティの危機/自然環境問題
もちろん、《豊かさ》はよいことばかりではありません。
「自由」というと聞こえはいいですが、裏返せば、さまざまな人や物との関係性から切り離されているということです。
私たち人間は、他者とのかかわりのなかで《自分》を実感していますから、こうした切り離しによって「アイデンティティの危機」に陥ります。
「主体性」というと聞こえはいいですが、裏返せば、「俺TUEEE」と勘違いした中二病の一種だともいえます。
そうした自然への傲慢な態度が、深刻な自然環境問題を引き起こしています。
こうした問題が《切り離し》に端を発しているなら、まず第一に関係性の見直しこそ大切でしょう。
現代文で、《切り離し》を批判して《つながり》を主張することが多いのは、こうした理由です。
ただ、単純に《つながり》を唱えることは、《切り離し》によって得られた近代の果実をも手放すことになります。
環境問題を声高に叫ぶことは簡単ですが、それを引き起こしている科学技術が私たちの生活を支えていることも忘れてはならない、ということです。
たとえば、原発。
いまだ、使い終わった放射性物質を処理できないにもかかわらず、建設され稼働しています。
だからといって、それを単純に否定することは、原発が生み出す電力によって成り立っている、私たちの今ある生活を否定することにもなります。
その生活のあり方まで含めて考えられなければ、本当の意味での《つながり》を考えていることにはならないでしょう。
人間と自然の関係を大切にしたい。
現にある《豊かさ》も大切にしたい。
この矛盾する願望を両立させることは決して簡単ではありません。
が、どちらかを単純に否定して答えを出した気になるのではなく、両立できないにせよ、どこに着地点を求めるか、深く考察することこそ、《つながり》を考えるということです。
ⅳ)《切り離し》→近代合理主義
「合理主義」とは、物事を合理的に考えることです。
「近代合理主義」もまたその通りなのですが、「近代」が付くかどうかで大きく違う点があります。
君たちも日ごろ実感していると思いますが、世の中のすべてを合理的に説明などできません。
不合理としかいえない部分がどうしてもあります。
そうした不合理な部分まで抱え込んで、合理的であろうと苦しむのが本来の「合理主義」だとすれば、「近代合理主義」は、その部分を切り離して、残りの部分を合理的に説明します。
「近代合理主義」は、いわば《切り離し》の論理です。
都合の悪い部分は無視するのだから、「近代合理主義」は非常に明快です。
が、都合の悪い部分を無視したために、後々矛盾が生じることも多々あります。
科学が非常に明快に見えるのは、この「近代合理主義」に基づいているからです。
悪くいえば、説明できなそうなところは見なかったことにする。
たとえば、科学が扱う自然からは人間が排除されています(デカルト二元論)。
科学が自然のしくみを明らかにしようとする過程には、常時、科学者という人間がかかわっているはずです。
が、それを言い出すと、科学の客観性が損なわれてしまう。
だから、ないことにしているのです。
では、人間を抜きにした自然のしくみを人間が使ったら、どうなるか。
その矛盾こそが、自然環境問題が起こる根本原因です。
それを解消するには、なかったことにしていたものを、まず、あると認めることでしょう。
だからといって、それは、これまで「近代合理主義」が築いてきたことを否定することではありません。
むしろ、その「近代合理主義」すら取り込んでいこうとする。
それが《つながり》の論理であり、本来の「合理主義」です。
ⅴ)ポストモダン
近代を「モダン」と呼ぶのに対して、現代を「ポスト・モダン」と呼ぶことがあります。
「ポスト」とは「後の」という意味です。
もし、現代が近代を乗り越えた後の時代だというのなら、近代のもっている視野の狭さをどうにかしなければならないはずです。
《豊かさ》という概念も、もともと、物の「量」の多さが基準となっていました。
だから、いかに大量生産でき、大量消費できるか、が《豊かさ》の指標だったわけです。
が、最近では、「量」ではなく「質」が問われるようになっています。
十分にご飯を食べられないとき望むのは、まずおなかいっぱい食べられること、つまり「量」です。
でも、十分に食べられるようになったら、次は、何を食べるか、ぜいたくが言えるようになります。
おいしいものを食べたい。
それは人によって違う。
さまざまな人が自分好みのもの、つまり「質」を求めるようになりました。
世の中の人たちみんなが量的に豊かになることをめざしたのが近代だとしたら、現代は、一人一人が質的によいものを求めるようになりました。
こうした多様性を認めることが「ポスト・モダン」の特徴です。
かつて医学は、延命を至上命題としました。
一秒でも長く生きていることをよしとしていたわけです。
が、今では、終活として、延命治療にNOと言うお年寄りも増えています。
命の長さより、それぞれの人の生の質、QOL(quality of life)こそ大切だと考えられるようになったからです。
先にも述べたように、《切り離し》を批判して《つながり》を主張するのが現代文の特徴です。
「一」を批判して「多」を主張する、といってもかまいません。
ここでも、「量」だけを重視することを批判して、さまざまな「質」を求めようと主張していることに注目してください。
ⅵ)村→国家→世界
近代は、社会全体が豊かになっていく時代です。
それにしたがって、経済的な社会単位も大きくなっていきます。
近代以前には、人々は、村という共同体のなかで暮らしていました。
が、それは、経済的に貧しいからこそ、みんなが互いに支えあい助け合って生きていく社会の大きさとして、村という小さな規模が適当だったからでしょう。
近代になって、豊かになっていくと、より大きな経済単位が必要になります。
それが、国民国家です。
私たちは、村の一員から国民になりました。
が、より豊かになっていくと、より大きな経済単位が求められます。
それが、グローバリゼーションという動きです。
経済単位が国家から世界へと拡大しようとしているのです。
もちろん、現在でも、国家という社会単位はまだまだ健在です。
しかし、私たちは、世界中からやってくる物や音楽なしには生きていけないし、他国で起こっている戦争にも無関心ではいられません。
少なくとも今現在の時点でいえることは、、、
私たちは、国民であるとともに、世界の一員であることも否定できない、ということでしょうか。

大前 誠司 編著
1,430円・四六判・328ページ