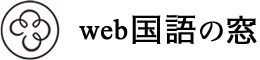評論文読解のキーワード「情報」
1-2-17「情報」
ここでは「情報」についてお話します。
特定の会社名を出さないようにしているので、少しまどろっこしいですが、我慢してください。
①情報化社会
ⅰ)何でもかんでもネットです
ネット通販、やりますか。
改めて考えてみると、私の買い物は、ほとんどネット経由です。
本も、机や椅子も、食料品や飲料も、ライブチケットも。
でも、安いからといって知らない店で買うのは、かなり勇気が要ります。
ネットで行われる個人間の売買も、私は信用しません。
私たちは、あらゆることが情報となってネット上を行き交う時代に生きています。
その情報をうまく使いたいけど、情報に振り回されたりだまされたりするのはいや。
だから、情報とのうまい付き合い方が必要なことはいうまでもないでしょう。
ⅱ)情報を確かめる
私は、わからないことがあったら、すぐにネットで調べてしまいます。
が、そこで気をつけているのは、2ヶ所以上で調べること。
確かめること。
それでも、たしかだとはいえない、とできるだけ保留するように心がけています。
というのは、ネットで出てくる情報は、あくまでもその物事の一面でしかなく、出来事の背景や具体的な状況など、十分にわかるわけがないからです。
もちろん、それはテレビや新聞などのマスメディアで報道される情報も同じです。
書籍に書かれている内容も同じです。
ⅲ)情報の断片性
私たちが手に入れる「情報」は、たとえ事実だとしても、物事の断片にすぎません。
そこには、まるっと生身の人間が欠けています。
だからでしょうか。
その表面的な情報にもとづいて、人は無責任に噂したり批判したりします。
そこには生身の人間がいないのだから、好き勝手言えるでしょうし、それによって傷つく人間がいることすら忘れているかもしれません。
そして、こうした個人の感想もまた、情報として、ネット上を駆け巡ります。
実は、こうした事情はネットの専売特許ではありません。
事件の被害者や加害者として、あるいは、その関係者として、テレビや雑誌などマスメディアに取り上げられて傷ついた市井の人がこれまでどれほどいたことでしょう。
インターネットの普及は、この「メディアの暴力性」を一人一人の人間に与えてしまった、といえるかもしれません。
質の悪いことに、発信者の名前を伏せる匿名性が高いことも、それに拍車をかけているようです。
ⅳ)分断の時代
マスメディアでは、建前として、さまざまな意見を取り上げなければならないことになっています。
が、ネット上では、そのような規制はありません。
あるところでは賛成ばかりがコメントされ、別のところでは反対ばかりがコメントされ。
個人も自由に発信できるようになったのがインターネットのよいところだといわれます。
が、そこに生まれたのは、期待されたような自由闊達な議論の場ではなく、気の合う同志たちが集まって、自分たちにとって耳触りのいい話が行き交うコミュニティ、いわば閉ざされた仲良しグループでした。
インターネットは、世界中の人たちが交流する場ではなく、むしろ社会を分断する場になっているようです。
それが現実の社会の写し絵になっていることは否定できません。
ⅴ)情報のバイアス
情報には必ずバイアスがかかっています。
たとえば、22年に始まったウクライナ戦争。
日本で見るかぎり、ロシアが一方的に悪者だとされています。
が、実際には、ロシアを支持している国や中立の立場の国はかなりあります。
日経新聞によると、批判・支持・中立の割合は、それぞれ1/3とのこと。
どの立場に立って発信するかによって、出来事はまるっきり見え方が変わります。
それは、私たち自身が発信する側になっても同じです。
もし私たちが情報に対して誠実であろうとするなら、自分がどのような立場で物事を見、発信しているか、自覚する必要があります。
ⅵ)本当かウソか
その情報が本当かどうかの見きわめも難しい時代です。
AIの発達によって容易にディープフェイクが作られ、その映像が本当なのかどうか、なかなかわからなくなっています。
さらに、生成AIは学習したデータから新しいコンテンツを作り出しますが、その元となったデータが本当とはかぎりません。
私たちには、その映像が、本当なのか、ウソなのか、それとも、一部ウソが紛れ込んだ創作物なのか、区別がつくはずがありません。
ⅶ)メディア・リテラシー
このように考えると、私たちは情報に対してかなり慎重にならないといけないことがわかります。
情報を読み解く力、「メディア・リテラシー(media literacy)」が必要なのです。
が、それは簡単なことではありません。
いわゆる「振り込め詐欺」に引っかかるお年寄りをバカにする傾向があります。
所詮、情弱なんだと。
たしかに、その情報が正しいのか、確かめる、という基本的なことができていません。
しかし、他人事ではないかもしれません。
たとえば、出前アプリには、たいていお得な初回割引クーポンがついています。
お得な1回だけ、と思って利用した結果、その後も思わず使い続けて高額な出前料金を払ってしまうなら、はたしてその人は情報強者なのか、情報弱者なのか。
私たちは、情報にあふれた社会に生きています。
まさに玉石混交。
が、その情報から逃げるわけにはいきません。
常に疑うこと。
情報もまた「知」である以上、それが私たちの最低限しなければならないことでしょう。

大前 誠司 編著
1,430円・四六判・328ページ