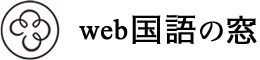評論文読解のキーワード「文化/文明」
1-2-12a「文化/文明」
ここでは、「文化」と「文明」についてお話します。
まず、「文化」と「文明」がどう違うのか、考えましょう。
①「文化」と「文明」
ⅰ)語源的な意味:文化⇔文明
「文化」の語源は耕す(cultivate)です。
人間が生きているために、大地としっかり向かい合っているイメージがあります。
一方、「文明」の語源は都市化する(civilize)です。
建物や道路、水道など、物質的に豊かで、見た目が立派なイメージがあります。
だから、文化も文明も〈人間の生の営み〉を意味する語だとしても、そのイメージはかなり違います。
文化は精神的で根源的、文明は物質的で表面的。
たしかに、「文明の利器」というと、パソコンとかエアコンなど、物質的なものを思い浮かべますし、「日本文化」というと、日本人の生活を昔から支えているもののように感じます。
こうした精神と物質を区別するデカルト二元論的な発想は、明治期の文明開化にも見られました。
それを「和魂洋才」といいます。
日本の魂を大切にしながら、西洋の技術を採り入れよう、というスローガンです。
ⅱ)文化=文明
もちろん、そんな都合のいいことは起こりません。
西洋の技術を採り入れ物質的に豊かになった近代日本は、大正デモクラシーに見るように精神的にも西洋化していきます。
〈人間の生の営み〉において、精神的なものと物質的なものを簡単に切り離せるわけがありません。
文化が精神的なものであり、文明が物質的なものであったとしても、それらは互いにかかわりあっていますから、区別する意味などほとんどありません。
最近では、文化と文明を区別なく使う場合も多々あります。
ⅲ)文化⊃文明
しかし、文化と文明には、やはり使い分けがあります。
たとえば、「文明開化 」、「ヨーロッパ文明 中心主義」。
この場合、「文明」を「文化」に言い換えることはできません。
この「文明」は、ともに近代ヨーロッパと深くかかわっています。
たとえば、「中国文明 」。
いわゆる四大文明の一つですが、これは近代ヨーロッパが見出したものであって、だから、「中国文化 」というと違う意味になります。
一方、「文化 相対主義」とか「多文化 主義」というとき、「文化」を「文明」に言い換えることができません。
ここでいう「文化」は、近代ヨーロッパにかぎらず、さまざまな地域、時代を視野に入れています。
ということは、「文明」は、〈人間の生の営み〉である「文化」のうち、近代ヨーロッパとかかわっているものを指す言葉だといえます。
しかし、現在では、そうした近代ヨーロッパ中心の文明観から離れて、「文明」が再定義されています。
ある文化を担う勢力が強大化し、周りを自分の色に染めようとする(ブルドーザ効果)とき、「文化」は「文明」になる。
だとすれば、近代ヨーロッパ「文化」が「文明」と呼ばれたのも納得がいくはずです。
ところで、文明にそうした暴力性を認めると、いわゆる「文明の衝突」は避けがたいことになります。
2001年9月11日に起こったアメリカ同時多発テロもまた、西洋文明とイスラム文明の不幸な衝突の一つといえます。
グローバリゼーションというのは、結局のところ、西洋文明が世界標準になっていく過程です。
それが進むなかで、世界は衝突を繰り返していくのか、それともそれを乗り越えることができるのか。
現代は、「国家」という枠組みが問い直されていると同時に、こうした「文明」という枠組みも問い直されている時代だといえるでしょう。
1-2-12b「文化/文明」
「文化/文明」の第2弾は、「文化」という語のもつややこしさについて考えます。
②文化
ⅰ)本能
日常での会話やライトノベルなどでは適当に使われていますが、、、
人間について語るとき、「本能」や「本能的」という語の取り扱いにはかなり注意が必要です。
本能とは〈遺伝的に決まっている行動のパターン〉、生まれつき決まっていて変えられないもの、です。
動物は、その行動のほとんどを本能によって行っていると考えられています。
ところが、人間の何気ない動作や行動も、実は文化的なもの、学習されたものです。
考えてみると、人間が生まれて最初に教え込まれるのはおしっこを我慢することです。
おしっこって、生理的な現象、、、のはずですよね?
歩き方も教育されたものです。
もともと、日本では、右足と右手、左足と左手を同時に出す、いわゆるナンバ歩きが普通でした。
田んぼのなかを歩こうとすると、自然とそうした歩き方になります。
今のように、左右の手足を交互に出す歩き方は、明治以来の学校教育の結果です。
おしっこや歩き方のようなものすら、文化的なものだということです。
私たち人間は、本能ではなく文化によって生きています。
それはどうしてでしょうか。
本能は、遺伝子によって、親から子へ、世代的に遺伝する先天的なものです。
それに対して、文化は、言語によって、社会的に遺伝する後天的なものです。
生物が生き残るためには、環境の変化に対応しなければなりません。
人間は、たとえば、新型コロナのパンデミックの際、世界中の人々が知恵を出し合い対処しました。
それが言葉によって世界全体に伝わり、少なくない犠牲は出ましたが、多くの人が生き延びました。
が、本能に頼っている動物は、そうはいきません。
新しい環境に適応する個体だけがわずかに生き残り、それが次の世代を担っていくことになります。
そう考えると、文化は、その柔軟性やスピードにおいて、本能を圧倒しています。
人間は、文化を得た結果、本能に頼れなくなったわけです。
ただ、そのスピードこそが自然環境問題を起こしているという指摘もあります。
毛虫が葉っぱをかじって木を枯らしても、ビーバーがダムを造って川をせき止めても、環境を破壊するほどにならないのは、その自然破壊のスピードがほどほどだからです。
が、人間は、自然の想定している以上のスピードで環境を変えていきます。
それが、自然環境を破壊しているというわけです。
ⅱ)言語
「文化」と表裏一体の関係にあるのが「言語」です。
私たちは、言語を通して、世界を見ています。
その世界の中で生を営んでいるのが私たちです。
文化が〈人間の生の営み〉である以上、その根底には言語があります。
言語は、文化を伝えるただの手段ではなく、むしろ言語こそが文化を作り出しているといえます。
近代国家の成立に「国語」が必要だったのはそのせいです。
一つの言語を共有することで、一つの文化を共有する――それが、「私たちは一つの民族なのだ」という民族意識を醸成したわけです。
そのせいで、文化は、国家や民族を単位として語られてしまいます。
日本には、「日本文化」という一つの文化があるかのように語られてしまいます。
たとえば、鯨。
海には海の暮らし、山には暮らしがあります。
昔から鯨を食べる地域がある、そうした文化を持つ地域がある、というのはまちがいではないにしても、「日本古来からの食文化だ」と日本全体のことのように語るのはまったくのまちがいです。
が、そう思ってしまうのは、日本語という一つの言語を共有することで、日本文化という一つの文化を共有していると思っているからです。
でも、それは本当にそうでしょうか。
そもそも、日本語と一括りにしていますが、日本全国で一つの言語は共有されていません。
方言はもちろん、標準語と呼ばれる言語も地域によって微妙に違います。
それがそのまま文化の違いなのです。
文化は、人間の生の営みである以上、異なる地域で異なる人々が暮らしているなら、そこには違う文化が広がっています。
だから、「日本文化」と一括りにできるものなどなく、「日本の文化」という種々雑多ないろいろな色合いをもった文化が日本には広がっています。
その一つに鯨を食べる文化がある、ということに異論はありません。
ⅲ)自然
文化の対義語は自然です。
「人間」と「自然」が対義語だとわかるなら(デカルト二元論)、自然は、人間の生の営みである文化の対義語だとわかるはずです。
ややこしいのは、その文化が私たちにとってとても自然 に感じることです。
いわれてみれば、おしっこや歩き方は、たしかに学習させられた人為的、文化的なものでしょう。
しかし、私たちは日ごろそのようには思いません。
そうした所作こそが、日常生活を成り立たせている、私たちにとって当たり前なもの、きわめて自然なものだからです。
文化は、いわば「第二の自然」として、人間の生を成り立たせているのです。
結局、私たちの生は、文化によって生み出された世界によって成り立っており、それこそが私たちにとって自然といえるものなのでしょう。
だからこそ、それが本当は自然でないことに気づかずに、偏狭な文化観や民族観、国家観に陥ってしまう人が少なくないのでしょう。
ⅳ)歴史
「文化」を語るとき、同時に出てきやすいのが「歴史」という語です。
実は、歴史も〈人間の生の営み〉と定義できるからです。
ただ、文化が、〈人間の生の営み〉を空間的な広がりに沿って共時的にとらえた語であるのに対して、歴史は、時間の流れに沿って通時的にとらえたものである、という違いがあります。
詳しくは、「歴史」の項をご覧ください。
1-2-12c「文化/文明」
「文化/文明」の最終回は、近代以降の文化、文明を巡る状況です。
③グローカリゼーション
ⅰ)ヨーロッパ文明中心主義
近代になると、ヨーロッパは、世界中に進出していき、その多くの地域を経済的に、軍事的に支配するようになりました。
その結果、近代ヨーロッパ的な考え方が世界基準となっていきます。
それが「ヨーロッパ文明中心主義」です。
ただ、それは、世界の中心であるヨーロッパが一方的に周縁の国々に押し付けただけでなく、近代ヨーロッパの進んだ文明に憧れた国々が自ら受け入れたという側面も少なからずあることは見逃してはなりません。
明治期の「文明開化」は、まさにそのような憧れを孕んだ近代化でした。
そこには、進歩史観が潜んでいます。
進歩史観とは〈人間は進歩し続けていると考える歴史観〉です。
それは、中世の《貧しさ》を克服して《豊かさ》を得た近代ヨーロッパ人の実感だったのでしょうが、だからこそ、自分たちを頂点として、《進んでいる/後れている》という基準で人々の生活を序列化してしまいます。
いやそれどころか、「《進んでいる》俺たちは《後れている》やつらを教え導くべきだ」という使命感すらもっていました。
こうした「上から目線」を啓蒙主義といいます。
この進歩史観=啓蒙主義には、差別的な傲慢さがあります。
たとえば、現在の世界には、国民国家という国家しか存在しません。
それは、近代ヨーロッパが、自分たちの国家制度以外を国家と認めなかったからです。
その結果が、植民地支配であり、不平等条約です。
日本が不平等条約を解消できたのが、大日本帝国憲法が成立し、国民国家としての体裁を整えた後だということは偶然ではありません。
しかし、これは現代の日本でも無縁ではありません。
たとえば、発展途上国に学校を作ろうという募金運動。
《進んでいる》日本が《後れている》国の子供たちに手を差し伸べよう、というわけです。
その志自体は尊いものですが、それが現地の人たちの目線に立っているか、と問うことを忘れてはなりません。
でなければ、かわいそうな人たちを助けてあげている、という自己満足に陥る可能性があります。
ヨーロッパ文明中心主義のミニチュア版が自民族中心主義、エスノセントリズム(ethnocentrism)です。
自民族、自文化を中心として世界を序列化してしまいます。
異民族、異文化との関係を考えるときに、私たちはしばしばこの自民族中心主義に陥ります。
しかし、それはしかたのないことかもしれません。
私たちは、自文化から世界を見て暮らしています。
それがいかに歪んだものだとしても、そのなかにいる者にとって無色透明です。
ヨーロッパの思想や芸術には、イスラム教に対する偏見や憧れがあるといわれます。
これを「オリエンタリズム(orientalism)」といいますが、このような異文化への偏見を私たちは必ずもってしまうものでしょう。
ⅱ)文化相対主義
しかし、このような自己中な考え方では、異文化を理解できるわけがありません。
むしろ、自文化を絶対化してしまい、互いに傷つけあう事態にすらなりかねません。
他の文化にどう向き合うか、考えるために、私たちは、まずその文化のありようをその文化の文脈でとらえなければなりません。
それを「文化相対主義」といいます。
どの文化も等価値だから、他の文化に口出ししてはいけない、という話ではありません。
異文化とかかわる際には、その文化の実際の暮らしや考え方のなかでどう評価されるか、をまず考えろ、ということです。
でなければ、相互理解も交流もうまくいくわけがありません。
たとえば、海外旅行で現地の子供に親切にされたので、感謝の意を込めて、頭をなでたとしましょう。
が、それが大きなトラブルになるかもしれません。
一部の地域では、頭を触るのはとても失礼な行為です。
そのことを知らないでやったからといって赦されることではないですが、知らなければ、何でトラブルになっているのかわからないわけですから、言い訳すらできません。
ヨーロッパ文明中心主義は、ヨーロッパ文明という進歩のトップランナーがいて、それにどれほど追いついているか、で他の文化をとらえていました。
《進んでいる/後れている》という基準で、文化を時間的に序列化します。
一方で、文化相対主義は、さまざまな地域にさまざまな文化があると考えます。
文化を空間的な広がりの中で並立的にとらえるのです。
だから、ヨーロッパ文明中心主義が文化を通時的にとらえているのに対して、文化相対主義は文化を共時的にとらえているといえます。
が、文化相対主義にも、一つ大きな欠点があります。
それは、文化を、民族や国家という単位でとらえがちだということです。
たとえば、東京には東京の暮らし、大阪には大阪の暮らしがあります。
ということは、東京の文化と大阪の文化は違うということです。
いや、東京のなかでさえ、「東京文化」と一括りにしてはムリがあるでしょう。
同じように、京都というかぎられた地域の、貴族の1000年前の生活と、横浜市の住宅街の、一高校生の現在の生活を、「日本文化」と一括りにしてとらえるのは、あまりに不自然です。
日本には通時的にも共時的にもさまざまな文化が息づいていて、それを「日本の文化」と言えたとしても、「日本文化」と一括りにするのはかなりムリがあります。
その意味で、「多文化主義」は、それを乗り越えようとする側面をもっています。
大学受験にあたって、文化相対主義との厳密な区別は要りませんが、「多文化」という表現には、文化が安易に一括りにはできないような多様性をもっていることが含意されています。
ⅲ)ピジン・クレオール説
こうした文化の本来もつ多様性を明確にしてくれたのが、「ピジン・クレオール説」です。
仕事上、植民地で現地の人が話す、なまった宗主国語を「ピジン」といいます。
諸説ありますが、「business」が中国語風に訛ったといわれています。
が、そのピジンが植民地に広まって子供たちが身につけるようになると、「クレオール」といわれます。
クレオールは、母語となったピジンです。
ここまでの説明が宗主国目線だったこと、気づきました?
宗主国をA、植民地をBだとすると、「なまった宗主国語」であるピジンはA語ʼ(ダッシュ)でしょう。
が、B語風になまったのですから、裏からいえば、「なまった植民地語」、つまりB語ʼ(ダッシュ)ともいえます。
A語’でもあり、B語’でもある言語――ということは、A語でもなくB語でもないC語という新しい言語だと考えるのが、公正なとらえかたではないでしょうか。
こうした言語の成り立ちこそ、言語の実像であり、文化の実像だと考えるのがピジン・クレオール説です。
言語=文化は、常にさまざまな人とかかわりあい混じり合いながら、変化し続ける可塑的なものなのです。
その意味で、言語=文化の本質は《雑種》だといえます。
逆に、言語や文化、そして民族を語る上で、一番危ない言葉は《純粋》です。
そうしたものの純粋性を訴えるところには、血塗られた対立しかありません。
今までの歴史がそれを語っています。
ⅳ)グローバリゼーション
ところで、現在の世界は、グローバリゼーション(globalization)の名のもと、世界の一元化が進んでいます。
文化相対主義や多文化主義が唱えられながら、実態は、ヨーロッパ文明中心主義がさらに強化された状況です。
世界中が近代ヨーロッパ色に染められようとしています。
が、さまざまな色をもつ世界に白の絵の具を塗っても、白一色になりません。
元の色と混じり合ってやはりその地域独特の色をもつことになるでしょう。
世界は一元化しようとしても、決して一元化しないのです。
たしかに世界は一つになろうとしています。
が、地域性は決して失われません。
globalでありながらlocal、つまりglocalになろうとしています。
それを、「グローカリゼーション(glocalization)」といいます。
結局、世界は雑種だということです。
考えてみれば、文明開化もそうでした。
近代ヨーロッパ色に染まりながら、そこに誕生したのは、近代ヨーロッパとも違うこれまでの日本とも違う近代日本です。
グローバリゼーションの影響を受けながら、エジプトではエジプトの暮らしがあり、ブラジルにはブラジルの暮らしがあります。
文化が〈人間の生の営み〉であり、それがさまざまな人とのかかわりのなかでしか成り立たない以上、文化の雑種性は変わることがありません。

大前 誠司 編著
1,430円・四六判・328ページ